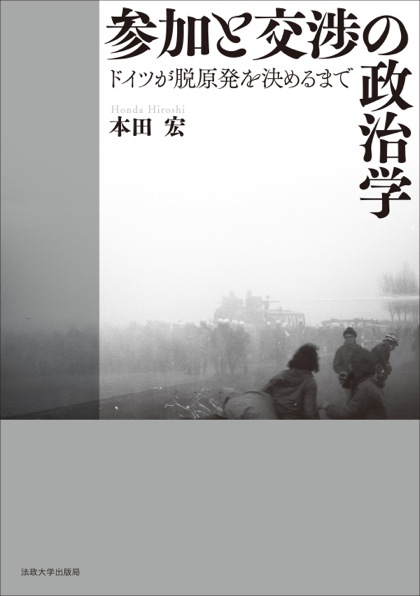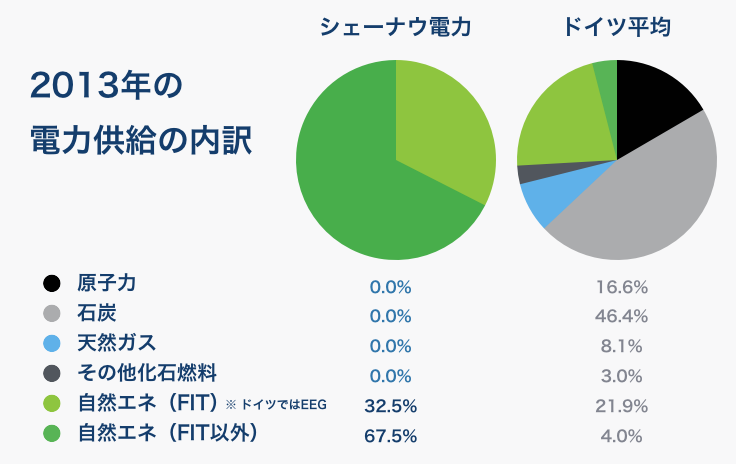エネルギーと社会のあり方が分散型へと変化していくなかで、個別の取り組みを長期的な時間軸の中で体系的に位置付ける思想、哲学、コンセプト、アイデアなどを探るEnergy Democracy Salon。今回は「3.11後の日本のエネルギー×デモクラシー」をテーマに、佐々木寛氏(新潟国際情報大学)のコーディネートのもと、小林正弥氏(千葉大学)×平川秀幸氏(大阪大学)×宮台真司氏(首都大学東京)の鼎談をお届けします。(2015年9月11日に開催された環境エネルギー政策研究所15周年記念シンポジウムより抄録)

佐々木 みなさんこんにちは、この鼎談のコーディネーターを務めさせていただく佐々木です。私は今日、新潟から駆けつけたのですが、この非常に喜ばしい日に招いていただいてありがとうございます。まずは、ISEP設立15周年おめでとうございます。心よりお祝い申し上げます。
新潟では「おらって」にいがた市民エネルギー協議会というものが去年の12月に立ち上がり、ちょうど9月23日に第1号の太陽光市民発電所を建設し、ようやくスタートすることになっています。ですから、ちょうど1歳ということで、ISEPが15歳ということですから、よちよちの赤ん坊が15歳のお兄さんお姉さんに指導されて今までやってきたということです。ISEPは「社会変革プラットフォーム」という役割を果たしてこられたわけですが、新潟でも、私たちの市民電力の試みを、本当に支えてくださいました。
私の専門は政治学で、民主主義論というものをやってきたのですけれども、この市民エネルギーの試みに参加しているプロセスで、恥ずかしながら今までの民主主義論というものがいかに貧弱であったかということを思わざるを得ません。現場でテキストにはない多くのことを学びました。今現場で進行していることというのは、民主主義論から見ても最先端のことだと私は思っています。文字通り「赤ん坊」のように、毎日毎日が新しい発見で、それを後で活字にしよう、本にしようと思うまま毎日が過ぎていきます。この経験はやがて政治学にしっかり還元しなければなと思っています。
今日はごく短い時間ですが、ここにいらっしゃる3人にデモクラシーとエネルギーについてお話をしていただきます。みなさんにご紹介するまでもなく、どの方も狭い意味におけるアカデミズムを飛び出して縦横無尽に活躍されている先生方です。それでは、小林さんから発題をお願いいたします。
臣民文化から市民文化へ
小林 今日はこういう記念すべき日に招いていただいて非常に光栄に思っております。私は今日、環境と平和に焦点をおいて、エネルギーとデモクラシーについての話をさせていただききたいと思っております。
本日9月11日で15周年ということをお伺いしましたけれども、9.11というとやはりアメリカの同時多発テロの日でもあります。これは、その後の世界、アフガニスタン・イラクの戦争につながり、そしてまた今それが中東地域の非常に大きな問題につながってきている。
そしてさらに3.11ですね。この9.11と3.11という流れは、世界に非常に大きな問いを投げかけてきている、簡単に言えば環境と平和において、従来の政策や社会のあり方が大きく動揺し混乱をする、そういう象徴であるわけですね。
日本でも東日本大震災、そして原発の問題の後、こういったことを無駄にしないで新しいものにつなげられないだろうかという問題提起が行われました。また世界の戦争の問題は、今日本において特に、集団的自衛権を容認するという安保法制の問題として議論されている所でもあります。ですから平和と環境というのはある意味では政治や経済にとって最も重要なポイントで、それが9.11、3.11といった日に問われるということになると思います。
そして私が今日、一番重要なポイントとして申し上げたいのは、デモクラシーとの関係において、これまで「日本においては市民文化がなく臣民的だ」、要するに「お上が決めたことにただ唯々諾々として従う文化だ」というように政治学では言われていたのだけれども、こういった事件を通じて、これから我々が直接政治や社会に関わるという「市民文化」への転換がようやく起こりつつあるのではないかということです。
例えば政治の問題を考えてみれば、現在の政権は、アベノミクスという経済の問題を訴えることによって成立した衆議院選挙の議席を根拠にしている。しかし、そのあと起こっている問題を考えてみれば、その時多くの人々が意識していなかった問題を議員たちが国会で通そうとしている。こういった議員中心の考え方のことを間接民主主義といいます。これは、人々が主権者なのだけれども直接決めるのではなくて、議員という代表を通じて間接的に決める、という構造になっているからですね。
間接民主主義には問題があって、選挙の時以外にすごく大きなことが起こって、重要なことを決めようとしたときに、主権者の意思とまったく食い違ってしまうのではないかという問題です。
これは政治思想の中では、ジョン・ロックという人と、ジャン・ジャック・ルソーという2人の意見の違いとして現れていますけれども、フランスで革命の思想を提起したルソーは、当時のイギリスの政治体制に対して「イギリス人は、自由だとおもっているが、それは大きな間違いである。彼らが自由なのは、議員を選挙する間だけで、議員が選ばれるや否や、イギリス人は奴隷となり、無に帰してしまう」と批判をしたわけですね。ですからそれ以外の時には、人々が集会などに出ることによって直接に参加し、主権者としての意思というものを明確にして行使することが大事だということになります。これは参加民主主義とか、直接民主主義と言います。
そして、こういった観点から見ると、今、エネルギーの問題、それから平和の問題を通じて、多くの人々の意思と国会における議席を代表する多数の意思とが大きく食い違っている。だからこそ、デモクラシーというものの原点に立ち返って、人々が改めて意見を出してかかわっていくという必要がある。今、国会の周辺で行われているデモなんかも、その表現の一つの形態であると思います。
そして私は、マイケル・サンデル教授の「ハーバード白熱教室」がNHKで放送されてから、正義の問題も、哲学の問題として色々と論じています。今日は時間が短いので、そういった正義の中身について詳しく立ち入ることはできませんが、いくつかの代表的な正義の考え方というものがあるのです。そして私は3.11の後に「原発の推進というものが果たして正義と言えるのだろうか」ということを色々な場で議論してきました。
結論から言いますと、当時は色々な議論があったのですけれども、今ではその結論というものは明確になりつつあります。当時の議論からすれば、専門家の間でも推進派と反対派がいて、議論が分かれてくる。だからこそ一般の人々が議論をしていって熟議の民主主義として決めていく必要があるということでした。
私は哲学的にそういう議論をおこなって、時間とか空間の観点、特に将来世代の観点やグローバルな観点から考えてみると、やはり原発の推進というのは、非常に大きな問題をはらんでいるのではないかと、こうした議論をそういった場でしたんですね。
そして、その後の展開を考えてみると、当時例えばコストの問題、あるいは原発なしにエネルギーは十分だろうかという問題も色々議論されましたけれども、結果的にはコストも原発は高いですし、エネルギーはそれがなくても十分に足りるということが明らかになりました。自然エネルギーがどんどん導入されていくということが分かってきたわけですね。
それからリスクの面を考えても、原発は立地周辺地域に特に大きなリスクを与えるという点で、非常に不正義です。一部の人だけに多くの問題を押し付けるという構造になっている。それからやはり、使用済み核燃料の問題や将来の大事故の問題を考えてみると、将来の世代に巨大な不正義を押し付けるということでもある。ですから、どういう思想的な立場から見ても、原発は結果的には不正義であるということについて非常に明確な結論が成立してきたのではないかと私は思っています。
マイケル・サンデル教授や私は、政治哲学のなかで、美徳とか共通の善というものを重視するような「コミュニタリニズム」という思想を主張しています。こういった考え方から見れば、やはり人間というのは環境の中に生きていて、人間は公共善・共通善という観点から環境の問題を考えてみる必要がある。そうすると、やはり正義に反するような原発は退けて、自然の中でエネルギーというものを自分たちの力でつくっていくという、エコロジカルなコミュニティの発想が大事だということになります。
そして政治学の世界では、民主主義と非常に深い関係がある「共和主義」という思想があるのですが、これは「みんなが公共的な関心を持って自分自身で決定し統治していく」という自治の思想です。一般には政治について言われることなのですが、私はエネルギーに関しても、自分たちで統治するという時代がきたと考えています。もちろん大きな電力会社が今後どうするかということについては、国家の決定が関係するわけですけれども、制度も改正されたので、自分たちがどういうエネルギーを使うかということについてはある程度は一般の人々の意思で決めること可能な状況が生まれつつあるわけですね。
ですからこういう点から見ると、エネルギーにおいて自己決定をして統治していくということが可能になる。これはある意味では民主主義が、国会とか議員に任せていくのではなくて、自分たちが直接決めていくという、そういう時代がエネルギーにおいても現れつつあるということの1つの例だと私は思います。
今、安保法案が大きな問題になっていて、毎週国会で採決しようという動きが進んでいますけれども、逆にいうとそれに対する反対の声というのも広がっている。
私は、あれはデモクラシーという観点から見ると人々が自分たちの力に目覚めて声をあげつつあるという新しい時代の始まりの面もそこにはあると思います。今回の国会でどう決まるのかということに関わりなく、日本の人たちが主権者としての意識に目覚めて、自分たちの運命を自己決定するという時代への流れ、大転換の流れというものが政治においてあるのでないかと思うのです。
もちろん私は議会を通じる民主主義、間接民主主義というものも大事だと思っているのですけれども、それが十分に機能しないとき、一般の人たちの意思とかけ離れたときには、直接声を上げるという直接民主主義をも通じたデモクラシーが必要ですし、今、ある意味ではそれが生まれつつある。それが、いまのエネルギーデモクラシー、さらには日本のデモクラシーの今後にとって、もしかしたら日本がこれまで経験していなかった新しい市民革命へと繋がっていくかもしれない。そういう希望を感じております。
佐々木 3.11という経験が、いわゆる民主主義そのものの再定義を迫っているというお話だったと思います。それから、先日9日に洪水のニュースもありましたが、民主主義に加えて、そもそも私たちにとって「安全とは何か」という問題も、現在再浮上していると思います。
例えば昨今の「安保法制」の問題も、私たちにとっての「安全」とは一体何であるのかを問いかけています。それから今小林さんがお話されたように、そもそも「正義」とは何であるのかという問題もあります。つまり、「民主主義」・「安全」・「正義」などの非常に基本的な概念が3.11後さらに問われています。またそれらの基本的概念の定義を決めるのは誰なのかという問題もあって、来たるべき新しい社会では、私たちひとりひとりがその決め方そのものをも決めていかなければならない。うかがっていて、現代はそういう状況なのかなと再確認しました。それでは次に、平川さんからお話頂きたいと思います。よろしくお願いします。
誰がどのように決めるのか
平川 みなさんこんにちは、平川です。私とISEPとの関わりはどちらかというと飯田さんとの個人的な関係です。現在、私は大阪大学に所属していますが、以前は京都女子大学というところにおりまして、そこで2000年に新しい学部が立ち上がり、飯田さんとはそこで同僚になりました。それ以来、ISEPも含めて飯田さんのさまざまな活動に注目し、いくつか関わりを持たせていただいています。今日はこちらに招いていただきまして大変ありがとうございます、誠に光栄です。
さて、今日お話しすることは、今の小林さんのお話にもつながる、そしてこの後の宮台さんのお話にもつながることかと思います。
「誰がどのように決めるのか」という問題、これが問われているんじゃないかという話ですけれども、例えば、今、国会あるいは官邸の前で、かつては2011〜12年にかけて、特に12年には、再稼働反対のデモが盛り上がり、7月29日には20万人集まったと言われています。
そして今回の安保法制をめぐっては、つい先日8月30日に、主催者発表で12万人集まったと。今夜もたくさん集まるのではないかと思われますが、これらのデモの中で問われているのは単に再稼働反対、あるいは安保法制反対ということだけではありません。シュプレヒコールやプラカードのメッセージを見ると、その中には「勝手に決めるな!」「私たちの声も聞け!」あるいは今の安保法制を巡るデモのなかでは「民主主義って何だ!?」というものがあります。
つまり、ある問題に関して誰がどのように決めるべきなのか、どのような決め方がより良いのか、政治学の言葉で言うと「正統性(Legitimacy)」の問題、これが問われているように思います。
しかしながら、そうした問いかけに対して現状の考え方、特に科学技術について常に言われるのは、科学技術の場合には中身は技術的、科学的、専門的な話が多いので「それは専門家に任せるべきだ」ということです。これは昔の話ですが、2000年、ISEPが始まった年の初めに行われた、徳島県吉野川の可動堰をめぐる住民投票でも、当時の建設大臣が「住民投票は民主主義の誤作動である」と発言しました。「可動堰が良いかどうかというのは、技術的に1+1がどこの世界でも2になるように、民主主義で決められないんだ」という意味でした。
安保法制をめぐっては、反対世論が強いことに対して、「国民の理解が不足している」「もっと丁寧な説明を」ということを政治家やマスコミがよく言っています。そう言いながらも、わけのわからない変な内臓みたいなおもちゃを使ってテレビで首相が説明して、余計わけわからなくなったりするんですけれども、こういう時に常に思うのは「理解が不足しているのはどっちだ」「説明が足りないのではなく、中身がおかしいのでしょう」ということです。
こういうことは科学技術についても常に言われてきて、そうした考え方のことを我々の分野ではよく「欠如モデル」と呼んでいます。どういう意味かというと、科学技術をめぐってなにか紛争が起きたりする、対立が起きたりする。例えば市民からの色々な不安が広がったり抵抗が生じたりすると「その理由は無知であるからだ」と処理しようとする考え方です。
市民が、例えば遺伝子組み換え作物に対して、原発に対して反対するのは、「それらの技術について科学的なことが分かってないからである、したがって、その正しい知識を分かりやすく教えてあげて、理解していただければ、その技術に対しての誤解も解け、受容が進む、受け入れが進むであろう」という考え方から、よく「ご理解ください」というセリフが使われたりするわけです。
しかしながら、実際には、さっき言いましたように、理解すべきはむしろどっちかということも多いわけです。さらに言えば、科学技術の問題というのは科学技術の専門的な知識があればそれですべて解けるかといえばそんなことは全然ないわけです。
例えば、科学的技術的な話についても、不確かさというのは必ずあります。なにが起こるかわからない、まだ詳しくわかっていないことがたくさんある。地震でも、原発でもそうです。
さらに言えば、先ほど小林先生のお話の中でもありましたけれども、リスクの分配をめぐる不正義といったようなことも含めて、実は技術の問題というのはさまざまな社会的問題、倫理や価値・人権・権利・正義といったことに関わる問題が含まれています。それは決して、科学的技術的な問題ではないわけです。
その意味では、科学技術の問題というのは実は公共的な問題です。先ほどの小林先生のお話の中にもあったかたちで言うと、世代すらも超えた、トランスジェネレーションな次元まで含めた公共的な問題として考えなければならないということになります。
しかしながらそれと同時に、今日の私の話として、後でまた順番が回ってきたときにも言及したいと思いますが、頭出し的に言っておきたいのは、先ほどの官邸前のデモや、それも含めた3.11以降の社会の動きの中で問われているのは、政府の側、あるいは専門家コミュニティの側での問題の処理の仕方、物事の決め方を変えること、科学技術の民主化、あるいは「専門性の民主化」ということだけではなく、民主主義の側の方もバージョンアップが必要なのだろうということです。我々自身の、市民としてのあり方も含めて変わっていかなければならないと思います。
それは大きく分けて2つのポイントがあるだろうと思います。1つは「市民社会の民主化」で、市民社会自体をもう少し、より民主的にしていかなければいけないだろうということです。
先ほどの小林先生のお話の中での言葉を使えば、臣民的政治文化ではなく、市民的な政治文化をもっと広めていく必要があるだろう。例えば今まさに会場(憲政記念館)の外で行われているようなデモが、もっとふつうにできる社会、デモに誰でも簡単に参加できる社会にしていくこと。これは、この3〜4年間の間にかなり達成できてきたと思います。
そしてさらに、それと同時に大事なのが「対話する文化」です。自分とは異なる考え方、自分が知らないテーマに関しても、学び、ほかの人からの意見を聴き、自分で熟慮し、そしてその意見を他の人に伝え、議論をし、対話をする。そうした試み、営みというのも民主主義の中で非常に根幹的な部分を占めます。長い日本の政治文化の蓄積の中からそれも育ってきたわけですけれど、これもこの4年間、特に3.11以降は原発をめぐって、あるいは安保法制、憲法をめぐっても、いろんなところで対話の試みというものが広がっています。
例えば安保法制を巡っては、私の知り合いもやっていますけれども「憲法カフェ」ということを若い弁護士さんたちがやっていたり、あるいは「怒れる女子会」ということで、女性の方々が、主婦の方たちも含めてあちこちで勉強会や対話の集まりをやっていたりする。その中で、テーマに関してのさまざまな学習をする。自らやったり、また議論をお互い深めたりする。違う考え方の人の考え方について、お互い理解しあったりする。そういうことが広がっています。
東日本大震災の被災地でも、復興をめぐって、地域で共和主義的なというか、自分たちで自己決定しながら自治でまちを再興していく、新たなエネルギーも生み出していこうという動きも広がっているわけですね。その基盤になるのが「対話する文化」であり、そしてその対話というのは何か特別な場である必要は必ずしもない。
例えば、政治学者でマンスブリッジという人がいます。その人が提案している概念で「熟議システム」というのがあります。システムというと何か固いものがイメージされますが、もっとゆるやかなもので、例えば先ほどの小林先生のお話の中でも出てきた「熟議」という営みというのは、何かかしこまった場でかしこまった顔をしてするものばかりではなくて、例えば日常の家族の団らん、友達との語り合い、近所の人たちとの立ち話、そういうことも含めて、さまざまな対話の営みが人の中に、社会に中にたくさんある。
それらがゆるやかにつながっていき、例えば選挙での投票であったり、あるいは何か直接的に意思を問われた時の意見表明であったり、市場での商品の選択、エネルギー源の選択、そういう機会における個々の判断に反映されていく。農業に例えれば作物に対する土壌や生態系全体の豊かさみたいなものを育んでいくような、そういう営みとしての対話の文化というものが結構大事なのではないか、これを今後どう育てていくかということが、一つ大きいのではないかと考えています。
あともう1つ大事なのは、市民社会の方も専門化が必要だということです。さっき「科学技術の民主化」「専門性の民主化」と言いましたけれども、それが進むためには、逆に我々市民社会の側もある程度の専門性を持つ必要があります。
例えば、ずっと反原発に取り組んできた高木仁三郎さんがかつて論文でおっしゃっていた言葉で「専門的批判の組織化」というのがあります。それを彼自身は、原子力資料情報室というかたちでやってきたわけです。またエネルギー問題ではISEPがこの15年間やってきたわけですが、こうした市民社会の側に根ざした専門的な組織、それに基づいた批判、そして新しいビジョンの提示、これを市民社会がどう育て、広げていくかということが、今後大きな課題かなと思います。
また細かい話などは後ほど話させていただきます。どうもありがとうございました。
佐々木 ありがとうございます。「民主主義のバージョンアップ」というお話でした。またその「民主主義のバージョンアップ」を支えるための基盤となるのが、対話の文化ということでした。ここまで予想以上にみなさん時間内で話を終えられているので(笑)、後ほどまた時間がありましたらさらに詳しくお話を伺いたいと思います。
続きまして、宮台さんからお話いただきたいと思います。よろしくお願いします。
共同体自治に向かう過渡期
宮台 僕は、いまお二人のお話をうかがいながら、話の構成を組み立てておりました。お二方の論点につながる話を幾つかできるだろうと思います。最初に、社会学あるいは社会科学の全般において、過去20年間、巨大システムへの依存は危ないという議論が、いくつかの側面から語られてきていることを、紹介させていただきます。大きく3つに分けられると思います。
一つはリスクマネジメントの観点です。レベッカ・ソルニットが東日本大震災の直前に書いた『災害ユートピア』(2009年)が震災以降、日本でも読まれるようになったので、御存じの方も多いかもしれません。巨大システムに依存しきってしまうと、人々は共同体的な相互扶助の習慣や実績を失ってしまいます。そこで巨大システムが壊れてしまうと、依存する度合いが高かった所ほど、共同体が元々持つ底力を使うことが出来ずに、人々が路頭に迷います。逆に、依存がほどほどで、共同体がポテンシャリティを維持していれば、巨大システムが壊れたとき「災害ユートピア」というべき相互扶助の花が開き、人々が内から湧きあがる力でお互いを支え合うということです。
巨大システムへの依存を批判する第2の観点は、ユルゲン・ハーバーマスから提起されているものです。彼はシステムと生活世界という言葉を使います。平たく言えば、「役割とマニュアル」で動いているのがシステムで、匿名的で、人の入れ替えがきくので、流動性が高い。生活世界は、ソルニットの「災害ユートピア」として具現するような、僕たちが元々営んできた「善意と自発性」に基づく、共同体感覚に満ちた営みということになります。
近代化とは、マックス・ウェーバーによれば計算可能性を増すような手続主義の貫徹への動きです。生活世界を営む我々が便利になるためにシステムを使うようになることです。我々が主人公で、システムが道具です。システムは計算可能性が高いので、管理がしやすく、投資がしやすいので、どんどん肥大していく。そして気がついてみると、主/従が逆転し、むしろシステムが主人公で、我々はシステムの作動部品、いわばリレースイッチのようなものに成り下がっている。これは疎外論的貫徹に立つ議論の典型です。
巨大システム依存を批判する第3の観点が、政治の暴走への危惧。グローバル化が進み、中間層が分解し、貧困化と格差化が進むと、民主制の健全な作動を支えていたソーシャルキャピタル−−対人ネットワーク−−が崩壊し、分断され孤立した個人が不安と鬱屈にかられ、感情の政治に釣られます。それを当て込んで政治が広告代理店的な動員戦略を駆使して人々を感情的に釣るので、政治は攻撃的で排外主義的になります。9.11以降のアメリカの暴走にも見られたし、小泉政権の際に政権に近かったコンサルが名指したB層–社会的弱者なのに自覚がない低IQ層–に訴求する昨今の自民党政治もそうです。
こうした、民主制の健全な作動を支えるソーシャルキャピタルの崩壊に抗うのが、先ほどお話しに出てきた熟議で、ジェームズ・フィシュキンが提唱したものです。彼の熟議論をベースにしながら、単に話し合うだけでは極端なことを言う声だけデカイ者が座を支配しがちだから、こうした集団的極端化を回避するための条件を付すのがキャス・サンスティーンです。集団的極端化を招く要因は、参加者の匿名性や、主題に関わる不完全情報や、座回しの拙劣さなので、これを回避するように慎重に運営されるファシリテーター付きの熟議が提唱されます。
まとめると、巨大システムへの依存は、第1に「リスクマネジメント上、あぶない」し、第2に「疎外という観点から、せつない」し、第3に「政治の暴走という観点から、あぶない」ということです。こうしたことは、しかし、3.11以降、とりわけ第2次安倍内閣以降、多くの方々が既に弁えておられるのではないでしょうか。その意味で、僕自身は、我々は希望に満ちた過渡期にいるのだと思います。多くの人は第2次安倍内閣を悲劇的に捉えすぎています。僕が安倍内閣を支持しているとかアベノミクスは素晴らしいということを言っているのではありません。
考えてみてください。もし第2次安倍内閣がなかったら、「憲法が、統治権力を制約するルールだ」ということをこれだけの日本国民がこの時期に弁えられたでしょうか。間違いなく弁えられなかった。憲法学者たちが今年2015年の7月に国会に呼ばれ、自民党が呼んだ長谷部恭男氏も含めて「憲法違反だ」と陳述しました。これが世論の流れが変わる大きなきっかけになり、学生団体SEALDsの動きもとても盛り上がりましたが、これも第2次安倍内閣があったればこそ。こうした流れの中で我々は「民主主義ってどういうものなのか?」ということを考え、議論するようになりました。
例えば、立憲政治とはどういうものなのか。「任せてブーたれる」政治から、「引き受けて考える」政治にシフトしないといかに議会が暴走するか。地方議会に「ローカル」という字をあてるべきなのか、それとも「ちほう」…あえて言いませんが(笑)。こうしたことがさんざん話題になった挙げ句、「こんな輩たちに任せていいのか」という気分が盛り上がって、国民過半数が反対する再稼働や辺野古や安保法制を恥じ晒しな政治家たちがどんどん決めていく状況に対するSEALDsの大規模な動きに繋がった。ニーチェではありませんが、悲劇の共有がなければ、人々は新しいステージに進むことができないという意味では、我々はやっと新しいステージに進みつつあるのかもしれません。
最後に、飯田さんと僕は、3.11の比較的直後の2011年夏に『原発社会からの離脱—自然エネルギーと共同体自治にむけて』という共著の書物を出しました。この本では、「任せてブーたれる」政治から「引き受けて考える」政治に僕たちがシフトするときの、一番分かりやすい手がかりが、「食の共同体自治」と「エネルギーの共同体自治」であることを紹介しました。日本の外側はもとより、飯田さんたちの試みを含めて日本の内側にすでにさまざまな実績があり、それを手がかりにすれば、僕たちが今から始めることができるということを述べました。
この「共同体自治」ということについて、『アメリカのデモクラシー』という本を書いたアレクシ・ド・トクヴィルというフランス人が、実は19世紀の前半から半ばにかけてすでに言っていたということを確認します。フランス人トクヴィルは、もともとデモクラシーに対して懐疑的で、フランス的な寡頭政治、つまりモンテスキューが言うような、偉い人たちが互いに牽制し合って政治をすればいいといった観点を支持していました。それがアメリカに行って本当のデモクラシーがあることを発見して衝撃を受けました。そこで彼は2つのことを発見したのでした。
一つは、本当のデモクラシーは規模が小さいからできるということ。つまり、えらい人たちに任せないで自分たちで引き受けられる範囲だから、本当のデモクラシーを実現できるということを見出した。「これくらいのまちの規模であれば自分たちでできるぞ」という構えを「タウンシップ」と彼は呼んでいます。もう一つ、このタウンシップのベースに、信仰共同体、つまり超越に関するプラットフォームを共有するという、重要なポイントがあることも言っています。超越の話は今日は話がずれるのでスキップさせていただきますけれども、規模が小さい、顔が見えるということは、非常に重要です。
巷には「顔が見えない範囲」を持ち出して「敵だ!」「味方だ!」と吠えるような、僕が「2ちゃん系ウヨ豚」と呼んで来た人たちがいます。ところが19世紀に初頭に遡れば、そういう輩はキチガイ扱いでした。19世紀の半ばになるまでは、見ず知らずの人間を思考停止的に「我々」だと呼ぶような作法は、クリスチャンやムスリムの信仰共同体を除けば、世界中一切なかったからです。そう、またしても信仰です。そもそもは17世紀半ばに、30年戦争という宗教戦争の手打ちで、ウェストファリア条約が結ばれて、「主権」すなわち「世俗的な最高性」という概念が出来たことが伏線でした。
しかし「主権」が生まれたとはいえ、この頃はsovereignが「諸侯」を指し、nationつまり「見ず知らずの我々からなる国民共同体」はなかった。手打ちの内容はというと、本当は世俗より超越が大切だし、社会より宗教が大きいけど、それを言うと殺し合っちゃうから、超越を世俗が選べる、宗教を社会が選べるという話に、嘘だけれどしちゃいましょうということ。そうは言っても選ぶの所詮は諸侯でしたが、二百年後、フランス革命後の混乱で、諸侯の弱体化で自分たちが攻め滅ぼされるのではないかと危惧した人々が、武器を持って立ち上がるところからnationつまり「国民国家」か出来あがりました。
しかし20世紀になって、手打ちユニットである「主権国家」が、最初は数百万人から最大で一千万人という規模のユニットだったのが、何千万とか何億規模になって、我々は完全に「顔の見えない範囲」で主権国家を民主主義で営むようになりました。そこで不可避的に採用されるのが議会制民主主義です。議会制民主主義といっても「顔の見える範囲」で営むのと「顔の見えない範囲」で営むのとはまったく違います。その違いがどんな弊害に繋がるのかが長い間にわたって覆い隠されてきました。トマ・ピケティが言うように、第二次世界大戦後20年余りの間、先進各国で経済成長が続いて中間層が膨らんでソーシャルキャピタルが個人を包摂したので、分断されて孤立した個人が不安と鬱屈ゆえに「感情の政治」に動員される大衆疎外状況が、緩和したことがあります。
ところが、グローバル化という名の資本移動自由化のせいで、「感情の政治」に踊らないで冷静な国民を支えてきた分厚い中間層が分解し、戦間期のように、分断されて孤立した個人が不安と鬱屈ゆえに「感情の政治」に動員される大衆疎外状況に見舞われる事態になりました。付和雷同的に煽られる人たちがどんどん増えているのです。だからこそ、「このままでは民主政がやばい」ということで、以前にも増して「任せてブーたれる」のはやめ、小規模なユニットからでも自分たちで「引き受けて考える」ことを始める動きも生まれています。
そういう「できることは自分たちでやる」という人間たちからなる複数のユニットが互いにコンヴィーヴ(共生)すること、すなわち、小林先生がおっしゃったような共和的な共生メカニズムとして、ミクロからマクロを構想することが、大事だという潮流に確実になってきているんです。日本でもその流れが今まさに進行中で、「任せてブーたれる」政治の中で、濡れ手で粟の利権を享受し、感情任せでブーたれてきた人たちの、いわば最後のあがきが展開している、それが安倍政権であり、ウヨ豚だと見ています。
佐々木 ピンチはチャンスでもあるということで、この会場にいらっしゃるみなさんは、もちろん宮台さんのおっしゃる「ブーたれる」方々ではなく、すでに自ら新しい社会を日々構築されている方々だと思います。
民主主義論で有名な政治学者でロバート・ダールという人がいます。その人が『規模とデモクラシー』という本を書いていますが、その結論は、規模とデモクラシーは関係ないというものです。しかし、私は、世界最大の原発がある新潟に住んでいてですね、その巨大システムとしての原発の存在そのものが、小林さんがおっしゃったような、そもそも民主主義の原理に反しているんじゃないかということは常々感じるわけですね。
また、1970年代、ロベルト・ユンクという人がすでに『原子力帝国』という本を書いていて、そもそも民主主義と原発は原理的に相容れないのではないかという根本的な問題提起をしています。つまり、宮台さんがおっしゃったように、エネルギーも含めて、巨大システムに任せていれば人生安泰だということではそもそもないんだということです。
その中で浮かび上がっているのが、飯田さんが冒頭でおっしゃったようなアソシエーション、これは「自発的結社」と訳していいのか分かりませんけれども、自らの発意で仲間を集めて、社会をつくるという、非常に古くて新しい民主主義のかたちに回帰しつつあるということかもしれません。そういうアソシエーティブな民主主義というものが再び注目されているということだと思います。
私も地元で市民発電に取り組む経験から、その民主主義を支えるものは何だろうということを常々考えているわけですが、宮台さんがおっしゃったようなコミュニティ、これはかつてのムラのようなコミュニティではなくて、新しいアソシエーションという意味でのコミュニティが必要であると実感します。
それから、これもなかなか言葉が見つからないのですが、ある種のつながりや絆、時間的なつながりというか、伝統的つながりと言っていいのか、倫理と言っていいのか、あるいはまた信仰といっていいのか分かりませんが、そういうものが、やはりこれからの民主主義にとって大事だろうと感じています。これは市民発電を実践する中で、例えば新潟であれば、新潟の昔持っていた記憶とか、伝統とか、そういうものが非常に重要であるということを再発見するわけです。
それから今まで出ていない議論としては、新しくできたコミュニティとかアソシエーション同士のつながりですね。個々のコミュニティが孤立して存在するのではなく、時には国境も超えてお互いリンケージして、相互に助け合ったりするというのが、新しい民主主義にとって非常に大事なのではないかなと感じています。
それでは、話が深まってきたところで、飯田さんが今日のセッションは未来を展望するセッションにしたいという事なので、もう少し先ほどのお話を深めながら、お三方から未来を展望するようなかたちで、エネルギーを媒介にいかなる民主主義が可能なのかということをお話いただければと思います。
コミュニティでの対話と熟議
小林 4人の議論に呼応する部分があると思いますので、そういったことを念頭に置きながら先ほどの話をもう一度深めてみたいと思います。
私の支持している思想は一般に「コミュニタリアニズム」と呼ばれるという話をしましたが、これは、人々が共に考える、共に行動するというように、コミュナルなものを重視するということです。ですから、「日本の古い、異質性とか異論を許さないような、前近代的と言われた共同体がいい」と言っているのではなくて、先ほど災害ユートピアの話とか、アメリカのトクヴィルが言ったタウンシップのデモクラシーの話がありましたけれども、そういった民主主義を支えるコミュニティを新しい次元で復興させていくという意味を持ったのがコミュニタリアニズムと言われる思想です。
さらに、海外ではしばしばコミュニティを人間のコミュニティという意味で捉えているのですが、私は、コミュニティの場、自然を含めたその環境のもとにおけるコミュニティを捉えていくことが、思想的には大事だと思っています。そういう意味では、エネルギーデモクラシーを自分のコミュニティで考えるというのは、思想的にも新しいチャレンジであると思います。彼らの議論に、日本の体験から新しい次元を付け加えるような、そういう意味も持っているのではないかと私は思っております。
そして、先ほど平川さんからも、科学技術に関する熟議の話がありましたけれども、ここでもある意味で日本は新しいチャレンジを行いました。民主党政権の末期ですけれども、海外の熟議民主主義、つまり、例えば専門家の間の議論というものを一般の人たちがしっかり聞いたうえで議論をする。そして意見がどのように変わるか。そういうことを実際に調査をしたんですね。これは政府も関わるかたちで行って、結果として脱原発の方向の人が増えたわけです。
これは実際、当時の民主党政権の政策にも影響を与えて、民主党政権、菅元首相は脱原発を主張しましたが、もっと穏当な立場ないし現状維持に近い立場を主張する人もいて、せめぎ合いはあったわけです。そういった熟議民主主義の実験の結果、やはり脱原発の方向を強めようという考え方が、政府としても打ち出されました。これは、全世界的にもさまざまなところで熟議民主主義の実験が行われている中で、政策に非常に大きな影響を与えた重要な例だと私は思っております。
そして、対話の重要性は常々私も主張しているところですけれども、今、原発の問題、それから集団的自衛権というような平和の問題において、人々の意識が目覚めつつある。
宮台さんの言葉を使うと、悲劇がもたらした良いこと、ポジティブなことだということでしたけれども、ある意味で我々は、そういった悲劇的状況を自分自身の力によって逆転させていく必要があると認識しつつある。
私もこの憲政記念館で、憲法をめぐる白熱教室をしたことがあります。当然、現在の政権の流れにおいて、今回の法案を通した後に憲法の改正そのものを目指そうという気持ちがあるので、この問題がさらに次の局面として現れるという可能性もあります。その時には国会議員だけで決めることはできない、つまり憲法改正においては国民投票が必要となる。だから、それまでにどこまで人々の間で熟議が行われて、人々の意識が目覚めているかが重要になります。先ほど私が言ったような、お上の言うままに従ってしまうような臣民的な意識ではなくて、自分自身が問題をしっかりと意識して変わる、そして行動するという、そういう民主主義が定着するかしないか、ということによって、その結果は変わってくると思います。
民主主義を巡る問題としては、最も重要なのはやはりクオリティ、質をめぐる問題です。つまり、民主主義の批判をする人たちは常々、「何も情報を知らない、関心を持っていない人がその時のムードとか、あるいは雰囲気に流されて投票するというようなものはよくない」と言います。そういう人たちから見れば、デモも、その時のムードに流されて、知識もなく、思考もあまりしていない人が時のムードでやっているだけだというようにしばしば言っているわけです。
私は、今日の局面ではむしろ、こういった直接政治に関わる人の方が本気で政治を考えていて、さまざまなルートを通じて情報を手に入れた上で、意思表示をしている人が増えていると見ています。だから民主主義のクオリティ、質が非常に上がりつつあるのではないかと思うのですけれど、そのための一番のきっかけになるポイントが、先ほどの対話の問題ではないかと私は思っています。
すでに民主党政権が成立した段階から言っていることなのですが、今日の日本の政治というものはものすごく大きな激動の時期にある。その前の自民党政権からの政権交代が非常に大きな変動だったわけですが、そこで日本の政治が一気によくなるというのは楽天的すぎると私は言っていました。
フランス革命の時を考えてみると、独裁政権に対してフランス革命が起こり、そのあとまたナポレオンの帝政になって、またもう一回革命がおこるという、すごく大きなジグザグなコースを進んで、歴史は展開していく。もちろんそういったことなしに安定的に発展していくというのが理想ではあるんですけれど、往々にして、こういう左右の大きな振れを通じて歴史は展開していくし、日本の政治あるいは経済は我々が好むと好まざるとにかかわらず、そういう大きな振れのなかで動いていくだろう、というのが当時の私の考え方でもあるし、今の私の見方でもあります。
ですから、政権交代があり、民主党政権の後、現在の政権になり、そして多くの人々が非常に危機感と関心を持って市民的な行動も行うようになる。そして、またこれが次の局面に展開していく。次の局面で、すべてオーケーでパーフェクトな理想的政治が現れるとは思わないですけれども、そういったさまざまな激動を通じて歴史が展開していくものと見ています。
最後に強調しておきたいのは、さきほどコミュニティ間の関係も大事だという話が出ました。やはり、小異、さまざまな考え方の違いはあるのですが、大きな、ポジティブな方向を目指す人たちが意見、違いというものをお互い尊重し合いながらもそれを超えて手をつなぐということが大事だと思います。
これは実際、脱原発の問題が盛り上がった時に、飯田所長などが中心になって日本の政治にも大きな影響を与えようという動きもされました。今また安保の問題をめぐって、野党間の結集という雰囲気も高まっています。ですから、こういった流れの中で、コミュニティを超えて、あるいはさまざまなグループを超えて、広い結集というものができていく。私はそれを「平和への結集」と言っていますけれども、それによって、政治の新しい局面がでてくるのではないかと、私は希望をしております。
対話の場と民主主義の質
平川 さっき最後の方で言った、対話の場、市民社会の民主化の話、民主政の専門家の話をもう少ししておきたいと思います。
対話の場について、さっき小林さんがおっしゃった民主党の末期にあったエネルギー・環境問題に関する熟議型世論調査があります。これは宮台さんがおっしゃったフィシュキンが考えて、アメリカなんかでは地方政治で実際に色々な実例があったり、また日本でも藤沢市とか地方の行政で使ったことがあります。
熟議型世論調査は、単に脊髄反射的にアンケートに答えるのではなくて、ちゃんといろんな意見の人たちと議論しながら、また専門家のいろんな情報提供やレクチャーなんかを聞いた上で判断して、アンケートに答えるという形式の世論調査なのですけれども、そうしたことを、国のエネルギー・環境戦略を決める過程で民主党政権が行いました。
これには実は、第三者検証委員会として、うちの同僚も関わっていました。少し無駄話をすると、新しいエネルギー政策・環境政策を決めるにあたって、国民的議論ということで何らかの熟議の取り組みを行うという話が、原発事故の直後くらいから出てきていました。しかし、それを具体的にどうやってやるのかはなかなか出てこなかった。いったいどうやってやるのだろう?やらないのかな?なんて思っていたら、突然ですね、2012年の6月の半ばに、資源エネルギー庁から、国民的議論を実施するための会社を公募する入札公告が出ました。しかも実施するのが8月の上旬であまりにも準備期間が短い。
我々研究仲間では、私も含めて、そうしたテクノロジーに関する市民参加型の評価、参加型テクノロジーアセスメントと呼ばれているものを、日本でもたくさんやってきました。これまでに30件以上実例があるのですけれども、そうした実例を踏まえて言うと、準備期間が一ヶ月半なんていうのはもうとんでもない、ありえないのです。
先ほど小林さんのお話のなかで、民主主義では質が大事だとありました。例えば、討論型世論調査で提供される情報・知識に偏りがないかどうか、きちんとバランスよく提供されているかどうか、正確であるかどうか。これを確保するというのは、単に専門家を集めるというだけでは済まない話です。非常に難しい、デリケートなプロセスです。それをきちんと確保するというのはそれなりに時間と手間をかけないとできません。そういうものをすっ飛ばして一ヶ月ちょっとでやろうというのはとんでもないと。
そういうわけで私ども研究者では、6月末に急きょ意見書を作成し、経済産業省と資源エネルギー庁に提出するとともにプレスリリースも発表しました。さらに、ちょうど私はその当時、朝日新聞の論壇時評の委員もやっていまして、たまたま私がコラムを書く回だったので、その中でもエネ庁、政府のやり方はあまりにもずさんであるという批判を書きました。そしたらこれらが、国民的議論を企画した国家戦略室の役人に響いたらしく、これはまずいということで、第三者検証委員会を設けて、国民的議論の準備や運営が公正に行われているかを見てもらうことにした、ということがありました。
これで何を言いたいかというと、実際に見えないところで、対話を政策決定プロセスの中に位置づけるという、そういう変化は起きているということです。それは、自公政権に代わったところで一気になくなってしまったのですが、そうした後戻りの変化というものも、さっきの宮台さんのお話で言えば、「これじゃまずい、我々が動かなきゃいかん、任せてばかりではいられない」というみんなの意識を、かえって強くすることにつながっているのだと思います。そういうふうに前向きに捉えれば、民主党から自民党に政権が移ってバックラッシュした、ということも含めて、まさに今過渡期なのだろうと思います。
その中で、我々市民社会の側でも、場合によっては政・官のなかでも、変化は起きつつあるのだと思います。そういうものをいかにつないで、次につなげるかということが大事かなというのが、言っておきたいことです。
最後に、民主政の専門化ということで言うと、やはり、我々が民主主義に大事な質を確保する上で、市民が物事を判断するための大事な情報や知識をどうやって確保していくのかという問題があります。そのために、市民社会の側で独立した専門的な機関、エネルギー分野であればISEPや原子力資料情報室だと思いますが、あるいは食品の安全性とか、環境保護、福祉とか、いろんな分野で市民社会の側に立った専門的組織をどう育てていけるかが重要なポイントになると思います。
そのために、我々自身も直接かかわらなくても、例えば寄付というかたちも間接的にはあるかもしれませんけれども、何らかのかたちで市民社会に根ざした専門性をいかに育てていくかというのは非常に大事だと思いますので、ぜひ、今後ISEPの活動を支える中で皆さんさまざま模索していただければと思います。
アソシエーショナルな協働性
宮台 小林先生がおっしゃっていた、道のりはそんなに簡単ではないという部分について申し上げます。僕は民主党の福山哲郎さんや枝野幸男さんと15〜20年位の付き合いがあり、この二人は、任せてブーたれる政治から引き受けて考える政治へという志向を強く思ってらっしゃる方々です。しかし2009年に民主党政権が誕生すると、さっそく週刊誌や新聞が「民主党政権に任せられるか?」という議論を始めたので、お二人と「うわ~、これはないわ〜」という話をした記憶があります。(笑)
佐々木先生がおっしゃった規模の問題について言いますと、20世紀の半ばに、ポール・ラザースフェルドという、元左翼から右翼に転じた有名な社会心理学者がいて、米国大統領選挙におけるマスコミ報道と人々の投票行動に関する『ピープルズ・チョイス』という本を書き、みなさんご存じのオピニオンリーダーという概念をつくりました。人々は小集団に帰属し、小集団の仲間から一目置かれる見識ある人=オピニオンリーダーが言うことに触れる機会が不可欠だ、とするものです。要は、個人が剥き出しで社会に晒されてはいけない、規模の小さいミニ社会に包摂されなければならない、というのです。
彼の議論は統計的分析をもとにしたもので、簡単に紹介するとこんな感じです。マスメディアの情報は人々を直撃するのではなく、人々が所属するスモールグループ(小集団)のオピニオンリーダーにまず咀嚼され、それをフォロワー層が受け取ることで妥当な解釈がシェアされ、民主政が健全に機能するのだと。中間層が分厚くなりつつあった当時を前提とした議論ですが、似たことを、ジョセフ・クラッパーというマスコミ効果研究者が言っています。彼も統計的分析を通じて以下のようなことを言うのです。
世の中にはメディア悪影響論が隆盛で、暴力的・性的コンテンツが議論になりがちだ。皆さんはこれを政治的扇動にまで拡張して理解しても構いません。悪影響としてコンテンツを問題にする人が多いが、それは間違いで、一人きりでメディアに接触していることや、接触した後に対人ネットワークの中でコミュニケーション機会が奪われていることこそ、悪影響の最大原因なのだ、とクラッパーは言うのです。現に、親しい人たちとテレビを見た人、見た後に親しい人たちと会話する機会があった人は、テレビの内容に直撃されず、妥当な受け取り方をすることが、見事に実証されているではないかと。
彼らの議論は、共同体自治的スモールユニットの、共和としてマクロを構想するのであれば、アメリカン・デモクラシーがうまくいくだろう、という話として共通しています。トクヴィルイズムという元祖アソシエーショニズムの妥当性を、あらためて再確認する、その意味で伝統的な内容なのですね。そのことを踏まえればこそ、現実のマクロで、いま何が起こっているのかが問題です。小林正弥先生を前にして恐縮なのですが、マイケル・サンデルの『アメリカのデモクラシー』という本を5年前にゼミで英語でみました。この本はこれから紹介するような議論をしています。
アメリカのリバタリアニズムのルーツにタウンシップがあった。それはコミューナルなベースだった。ところが産業化や都市化でコミューナルなベースが崩れ、タウンシップの相互扶助がうまくいかなくなった。そこでマクロな政治的再配分が要求され、リベラリズムが出てきた。でもリベラリズムはタウンシップの本義に反する。実際アメリカでリベラリズムというと、国家的再配分主義という否定的ニュアンスです。そこで本来のアメリカに戻るべきだとバックラッシュが生じ、リバタリアニズムが出てきた。でもかつてのコミューナルなベースがないから、市場原理主義者のようなダメな人たちが出てくる。それが現在の絶望的なアメリカなのだと。僕の弟子が先日話を聞きに行ったのですが、サンデルは白熱教室の時は明るいけど、根は暗いそうです。(笑)
それはともかく、僕が申し上げたいのは、コミューナルなベースとか、国家と個人の間にある中間的な共同体というと、つい昔ながらの共同体を思い出しがちですが、さきほどからアソシエーショナルなものが話題になっているように、無自覚で思考停止的な共同体に埋め込まれるのでなく、民主制を健全に回して政治の暴走を防ぐためにどんな機能が必要なのかを深く分析し、剥き出しになった個人が「感情の劣化」を被らないようなプラットフォームとして、規模の小さなミニ社会を再帰的・自覚的に構成しなければいけないということです。フィシュキンが言う熟議の目的も、「引き受けて考える」構えの醸成や、声のデカイ極端者が場を支配できないような完全情報化や非匿名化に加え、「新しい我々」を構成する点にあります。
老人なんて頑固だと思ったら、意外に柔軟じゃないかと。在日や中国人は反日的だと思ったら、立派な意見を言う人もいるものだと。浅ましい日本人より、立派な外国人の方が話し合って稔りがあるなと。すると「今までの我々感覚って違うじゃん、本当の我々は別じゃん」と我々が再構成される。今まで縦割化して話す機会もなかった人たちと話す機会を持てばこのような「経験を通じた成長」ができる。つまりデューイに代表されるプラグマティズムの民主主義観が熟議論に流れ込んでいます。トクヴィルイズム、プラグマティズム、コミュニタリアニズム、熟議主義は、互いに関連しながら同じものを指し示します。小林先生や平川先生も話題にしておられる、長いものに巻かれる的共同体ではない、境界線の絶えざる引き直しを伴うアソシエーショナルなコミュニティです。
もはやお上に任せられないというのは、複雑な社会システムを生きる我々の、国境を越えた共通感覚だと思います。けれども、サンデルが危惧していたように、我々の手元にコミューナルなものがなければ、お上に任せられないとなったときに直ちにホリエモン的な市場原理主義がせせり出して来ることになります。現にそうなっていますよね。これは、格差化と貧困化、個人の分断による孤立化、不安と鬱屈による「感情の政治」、攻撃性と排外性の上昇などを招き寄せる、あからさまに間違った選択です。これを回避するための唯一の道が、境界線の絶えざる引き直しを伴うアソシエーショナルなコミュニティと、コミュニティ同士のコンヴィーヴです。それを強調して僕の発言を終わります。
佐々木 さきほどうかがったところだと、ISEPが設立会合をもたれたのは今日からちょうど15年前の2000年9月11日だということです。
9月11日は冒頭の小林さんのお話にもあったように、世界同時多発テロの日付ですが、それ以後の世界はまさに1990年代から予言されていた「文明の衝突」が実現してしまうという状況にありました。その後、ご記憶のように、いやいや「文明の衝突」じゃなくて「文明の対話」であるべきだというハタミ大統領のような人たちが出てきて、衝突か対話かという議論になったわけです。今日のセッションの結論も、2015年9月11日、新しい可能性は、平川さんのおっしゃるような対話、非常に古い言葉ですがまさに「対話」にあるのではないかということでした。
そしてこの文明的対話をずっと媒介し、促進してきたISEPが、今では日本中の地域エネルギーの取り組みを繋げて、新しいデモクラシーの形を創り上げてきたのだ、ということを再確認して、このセッションを終わりたいと思います。3人の先生方どうもありがとうございました。
(編集/古屋将太)