「エネルギーデモクラシー」へようこそ
3.11福島第一原発事故のあと、いったんは脱原発に向かうかに見えた日本は、その後、安倍政権の誕生を契機に、混迷を極め、一気に視界不良となりました。福島で置き去りにされる原発避難者、「金目」(かねめ)で片づけられる除染廃棄物の中間貯蔵問題、放射能被ばくの健康影響調査の「闇」、福島第一原発での凍土遮水壁の失敗と果てしなく続く事故処理、「原発は重要なベースロード電源」で論理破たんしているエネルギー基本計画、住民避難計画から目を背ける原子力規制委員会など、どれをとっても不条理で乱暴としか形容しようのない手続きで原発再稼動や原発の再興が推し進められようとしています。
そうした不条理で不透明な日本の環境エネルギーの言論状況が覆う中で、この「エネルギーデモクラシー」では、歴史への基層となり、未来に向けた信頼できる「羅針盤」となる言論や思考の、銀河や電子雲のような集合体となればと願って船出します。
「環境ディスコース」を積み重ねる
日本の言論界(もしくは知識コミュニティ)での不思議は、歴史の「風雪」に耐えうる積み重ねが乏しいと思われることです。少なくとも、環境エネルギー政策の分野ではその傾向が強く、ほとんど「賽の河原」のように失敗が繰り返されます。
たとえば自然エネルギーの固定価格買取制度(FIT)の導入前に施行されていたRPS法の「失敗」、自民党の前政権(福田ビジョンなど)よりも後退した安倍「経産省」政権での気候変動政策、そして福島第一原発事故を経たのに「先祖返り」した、核燃料サイクルを筆頭とする「失敗のデパート」ともいえる原発政策などです。
粗い仮説ですが、その原因は次のようなことではないでしょうか。
「特定のテーマ」や「新しい問題」が浮上すると、国(経産省など)と電力会社などの間の駆け引きでアジェンダや落としどころが決まり、それが審議会やメディアなどに「振り付け」られ、細部は多少変わっても、おおむね「予定調和」で一件落着する。その過程は、事実や実証よりも、誰が何を言ったか、あるいは「言ったもの勝ち」のような粗雑な議論で埋め尽くされてゆきます。「ブーム」が終われば、「紙くず」のように忘れ去られてゆき、後には何も残りません。
他方、日本以外で見られる多くの知識コミュニティの態度は、少し違っているように思います。「特定のテーマ」や「新しい問題」に対して、立場や利害を超えた公共的な言論空間を創り、さまざまな仮設や検証や議論を重ねてゆき、概ねのコンセンサスを得た「確からしい解」(政策や制度、基準、原則など)に凝縮してゆきます。それを、これまでの「歴史的な知識の基層」の上に層を積み重ねてゆくような「社会的な知的作業」を行っている、という印象を持っています。これを私は「環境ディスコース(Environmental Discourse)」と名付けて理解しています。
ディスコースとは、社会的な言論活動の総体のようなものを指しますが、たんなる事柄の記述ではなく、無数の言論活動(ディスコース)を通じて、「共通意味世界」を構築してゆくものです。「環境ディスコース」とは、環境(エネルギー)分野における無数のディスコースの集積をとおして歴史的に構築され、積み重ねられてきた「共通意味世界」であり、たとえば欧州の環境政策(環境法、環境政治、環境研究など)の共通知識の基層となってきたと考えています。
左右でも市場原理でもなく「プログレッシブ」へ
かつて、原発や政府のエネルギー政策に批判的な言論は、「左翼的」(政治的リベラル)と見なされてきました。しかし福島第一原発事故は、「右の脱原発派」を生み出し、健全な原発論争を遮ってきた左右イデオロギーという「煙幕」に風穴を開けました。逆に、これまで「保守」の影にこっそり隠れていた「守旧」や「既得権益」を明るみに出したともいえるでしょう。
また、「改革派=市場原理主義(経済的リベラル)」という固定観念も排する必要があります。「改革」は民営化だけではなく、「民営化」や市場を活用することは必ずしも「市場原理主義」ではありません。
左右でもなく市場原理主義でもないこの場のエートスは「プログレッシブ」を一つの軸にしたいと考えています。「プログレッシブ」の辞書的な意味は「進歩主義的」ですが、創造的(クリエイティブ)、革新的(イノベーティブ)、未来志向といったニュアンスも織り込んだ、社会を望ましい方向に段階的に変えていく漸進的な考え方です。
科学技術はいやおうなく進み、人・モノ・カネ・情報の「グローバリゼーション」も進んでゆくにつれて、社会や組織、家族や個人のあり方や思考、価値観も変わってゆきます。そうした「変化してゆく社会」のなかで、環境と経済と社会・政治のすべての基盤であると同時にすべてに影響を及ぼす環境エネルギーを、現状のままで固定していては、矛盾や歪みは大きくなるばかりでしょう。環境エネルギーと社会を持続可能な方向へ、どのように段階的に変えてゆくべきか、漸進的な改革視点は欠かせないと考えています。
「現実」にコミットメントする
ここで大切にしたい姿勢の一つに「現実へのコミットメント」があります。民俗学者の巨人・宮本常一氏が「調査地被害」という言葉で、社会学者によるフィールドワークの姿勢を批判しています。要は、えらい学者さんが調査地に乗り込んで、相手の都合も構わずに根掘り葉掘り聞きたいことだけを聞き、挙げ句の果てに貴重な資料を借りだして、礼状の一つもなく、あげくにその資料を返さないことも多いことを批判したものです。
自戒を込めて言えば、原発・環境エネルギーなど他の分野でも同じようなことがあるのではないでしょうか。研究者や学者、活動家が何らかの課題やテーマに接する場合に、自分の論文や研究や本の出版、あるいは名声や社会的な立場といった、「自分の思惑」がないとは、言い切れないように思います。
「現状におもねる」のではなく、一人ひとりの暮らしや社会がどうあるべきか、そうした「現実にコミット」して、そのための公共政策がどうあるべきか、そこに自らがどう貢献できるか、徹底的に「現実」に拘り「現実」と格闘する公論が積み重なれば良いと期待しています。
大転換、そしてエネルギーデモクラシーへ
この10年、少なくとも環境エネルギー分野は「大転換」の時を迎えています。資源論的には、石油がすでに「生産ピーク」を超えつつあるとの観測があります(Nature 2012)。世界中の期待が盛り上がった2010年のコペンハーゲン気候サミット(COP15)も期待外れに終わりましたが、主要な温室効果ガスである二酸化炭素濃度が400ppmを超え、気候変動問題の危機感は高まっています。他方で、自然エネルギーが飛躍的な成長を遂げ、水力を除く発電量がついに原発を追い抜こうとしています。
そうした真っ只中に起きたのが、3.11東日本大震災と福島第一原発事故です。自民党前政権時代に「原子力立国計画」という時代錯誤の政策を打ち立てていた日本は、民主党政権に代わっても、事故の直前まで変わらずにひた走っていました。それが、福島第一原発事故の「衝撃」で粉々に打ち砕かれたわけです。
もう一つの「大転換」は、大規模・集中・独占型から、小規模・地域分散・ネットワーク型への、エネルギー体制の根底的なシフトがあります。この大転換は、とくに電力会社がほとんどの国で巨大資本であることから、構造転換を伴う大きな社会変容となります。
巨大独占電力会社が存在しなかったデンマークでは、比較的にスムーズにエネルギー体制の変化が先行して進みましたが、国を挙げて「エネルギーヴェンデ」を進めるドイツや35年も前に国民投票で脱原発を決めたはずのスウェーデンでさえ、政治的な合意で難航しています。そうした状況や日本の「今」を見ればはっきりと分かるように、エネルギー選択は「政治」そのものの大きな課題となっています。
「未来は予測するものではない、選び取るものである」(ヨアン・S・ノルゴー)
との名言のとおり、エネルギーと私たちの未来を選び取るための議論や思考を積み重ねてゆきたいと思います。











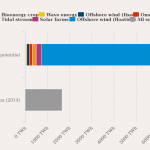
[…] 当研究所は、今後も歴史への基層となり、未来に向けた信頼できる「羅針盤」となる言論や思考の、銀河や電子雲のような集合体となることを目指し、Energy Democracyの運営を進めて参り […]