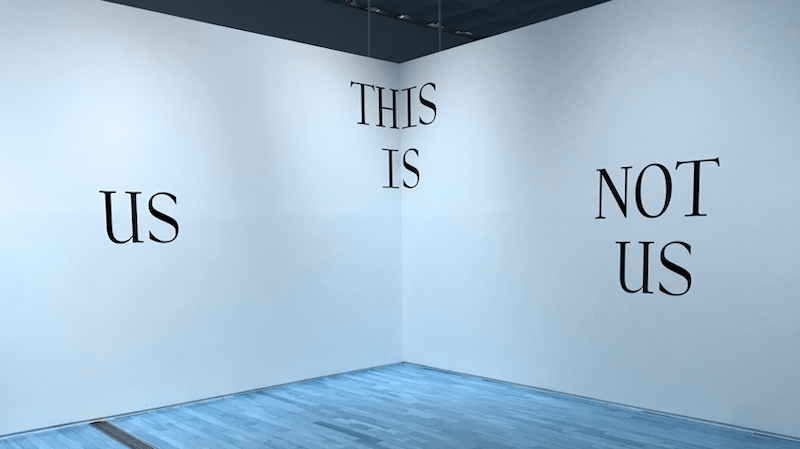先日、クロエ・ジャオ監督の長編デビュー作である前作「ザ・ライダー」をAmazonPrimeで鑑賞し、その感動の冷める間もなく、今年度アカデミー賞作品賞を受賞した「ノマドランド」を地元のシネコンで鑑賞してきた。
リーマンショック直後のアメリカが舞台。遊牧民(ノマド)として車で寝泊まりし、職を求めて国内を移動しながら生きている人々。かつて、新大陸のプロミスランド(約束の地)であった大地が、いまや、流浪の土地(ノマドランド)になっている。
しかし、グローバル巨大資本企業と使い捨て忘れ去られてゆく個人、というステレオタイプの社会批評的視座を主背景に使いながら、もう一段深く、現代人にとっての「生老病死」を真正面から考えさせる作品となっている。
主演賞を受賞したフランシス・マクドーマンドは、圧巻だ。
前作「スリー・ビルボード」でもその演技に圧倒されたが、今回は、映画冒頭、主人公が平原で小便をするシーンから映画がはじまり、体調を崩したシーンでは、ボロボロのバンの車内で、腹を下し、車外に出ることさえ間に合わずバケツに大便するシーンも演じる。
まさにとことんリアルに生きている等身大の私たちの生を正面から描く。しかし、彼女が演じると不思議とそんなシーンさえも暗い悲壮感一色に染まらないから、不思議だ。
数年前に夫に先立たれ、職を失っている主人公。すでに生活拠点もない街から遠く離れようとしないことに周囲は、疑問を持つ。それに対して、彼女は、妻である自分がこの土地に今も存在することで、愛した夫がたしかにこの町に存在していたことを周囲に証明し続けたいのだと静かに答える。
「さよなら」とはいわずに「いつかまた」と手を振り合ってそれぞれの目的地への旅へと別れるノマドという生き方には、生者と死者の区別さえない。
ノマドライフの精神的支柱でもあり、脱資本主義の新しい生き方であると70年代のヒッピー的自由と連帯の精神を提唱し、周囲を明るく励ます年配の男性が登場する。
ある日、彼が、5年前に当時32歳だった息子が、自殺していた事実を主人公にだけ密かに告白する。その苦悩から彼自身も、自死を繰り返し考えたが、しかし、自分が死んだら、息子を悼む人間がいなくなることに気がつき、それのみが自分の唯一の存在理由だ、と語る。
「社会的理念」を周囲に語る人も、実は、ごく「私的信念」の支えのみで生きている現実。生と死が渾然一体となり、死者が生者を支えているこの世界の実相。
印象的なシーンをもう一つ。
ガンの末期であるノマド仲間の友人である女性が、自分の生涯で巡り会った最も素晴らしかった思い出のカヤックに人生の最期にもう一度だけ、体調を復活させて乗りたいと語るシーン。
数ヶ月後のある深夜、シーカヤックのコックピットから静かに波間に指を触れる動画が、主人公のスマホのSNSメッセンジャーに送られてきた。メッセージも挨拶も何もないが、女性が、死を前に、もう一度カヤックに乗れたことを知り、深夜の車内で一人微笑む主人公。
主人公が、一枚の木の葉のように全裸で川に浮かび漂泊するシーンがある。自然と一体となり、洗礼を受けるように自然の美しさに抱かれ、孤独な魂を鎮める光景が印象的だった。
私たちはだれもが小さな光として、短い生涯を流れ星のように一瞬の光を放っている漂泊の旅人にすぎないのかもしれない。中国生まれで現在、39歳の女性、クロエ・ジャオ監督に静かにそう語りかけられているような心持ちになる。
すでにノマド的生き方を賛美する幻想を捨てたポストコロナの世界にこの作品は生まれた。翻ってみると、わたしたちは、ノマド生活さえ許されていない国に生きている。
プリズムのように光の当て方によって、さまざまな色彩を放つ名作。