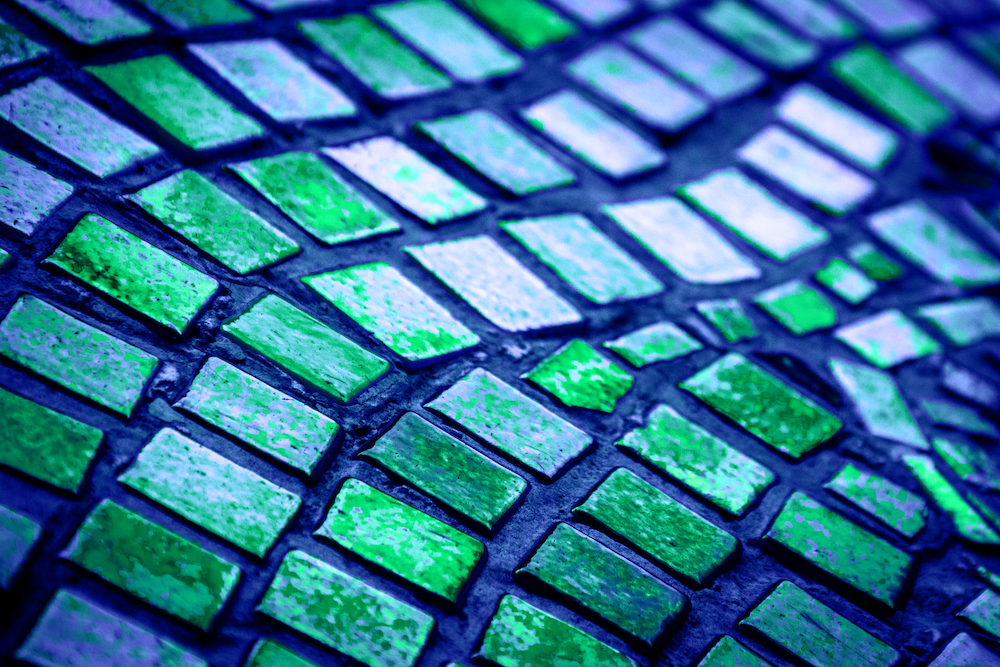2018年秋、こまばアゴラ劇場で、ISEP所長の飯田哲也さんと劇団青年団『ソウル市民』『ソウル市民1919』の連続公演を観劇した。
オリザ作品は、開場して観客が入場する段階で、すでに舞台では演劇がはじまっている。出演者が寝ころがり、あくびをするプロローグのような最初の短いシーンが、開演時間までリピートで演じられている。
しかも、こまばアゴラ劇場は、舞台と客席の間には段差がなく、小さな空間に膝を曲げた観客が、互いの肩を寄せ合って、舞台を囲んで鑑賞する丸く包み込まれるような演劇空間。まもなく観客は、現実世界の時間軸から解き放たれ、魔法仕掛けのような架空の世界にドップリと浸ることになる。
「リアル劇作家」平田オリザさんによって磨き上げられた、瑞々しいセリフの言い回しと生活感のある所作の一つ一つが、手を伸ばせば届くような距離で、繰り広げられる。
午後を目一杯使った長い連続公演の終演後、劇場から表の路地に出て、飯田さんに言葉を発した瞬間、驚いた。自分の声が、自分のものでない。
それは、よく耳にする映画館を出た観客が、主役の高倉健やジェームス・ディーンになりきっているという類いの、映画の主人公との自己同一化現象とは、似て非なる体験。
むしろ、自己の内面に巣くう、名もなき「他者」に気づかされ、はじめて対面するような戸惑いの経験であり、無意識に身にまとっている「社会的キャラ」の毛布を一枚一枚、剥ぎ取られ、裸にされたような胸のザワつきだ。
自分の口から発する言葉の一つ一つが、自分の「職業」や「ジェンダー」、「年齢」を背景にして、他者によって規定された脚本のセリフのようだ。
「ソウル市民三部作」のように、個人の自由とジェンダーや差別の時代の変遷による変化を立体的に浮かび上がらせるには、地理的座標軸を固定し、時間軸だけ移動させる手法が有効だ。
その意味では、昨年末から、Netflixで次々と公開されている劇作家オーガスト・ウィルソンの一連の作品にもそれは当てはまる。
オーガスト・ウィルソンは、現代アメリカの「黒人シェークスピア」と称され、ピューリッツァ賞の二度受賞をはじめ数々の演劇賞に名を残し、2005年に惜しくも60歳の若さで早逝されたアメリカ演劇界のレジェンド。
彼の遺した10本の演劇作品からワンシーンを選び独演する、モノローグ・コンテストは未来のブロードウェイ俳優を志す高校生たちの登竜門として、毎年全米から若き才能が結集する。(なお、この演劇祭の様子もNetflixにて鑑賞できる。一見の価値あり、お勧めしたい。(『Giving voice:内なる声が語ること』)
オーガスト・ウィルソン作品は、第1作目の『マ・レイニーのブラックボトム』の舞台が1920年代のシカゴである以外は、すべて彼自身が生まれ育ったピッツバーグの黒人居住区ヒル地区が舞台である。
近代資本主義の勃興と連動した急速な工業化と都市部への人口の流入によるスラム化に至った街の小さな居住区の何気ない日常を、20世紀100年間の各時代から切り取り、全米で上演され、作品のいくつかは映画化もされた。
現実に厳しい黒人差別に囲まれながら、一個人が、自分の生まれた時代の中で自己をどう定義づけて、社会を生き抜こうとしていたのかをリアルな台詞回しと、ブルースやジャズ、ソウルミュージックなどの豊かな黒人音楽と融合させて描き、高く評価された。
(なおオーガスト・ウィルソンの興味深い生涯は、桑原文子による書籍『オーガスト・ウィルソン:アメリカの黒人シェイクスピア』に詳しい)
「マ・レイニー〜」では、才能溢れるトランペット奏者の若者が主人公。彼は、幼少期、母親が白人から集団暴行を受け、後日、復讐を企てた父は、リンチで殺害され、木に吊らされた。彼はそのすべてを目の当たりにして育った。時は1920年代、ブルースから未来のジャズが生まれる。音楽の未来が見える青年にとって、その唯一の可能性への夢を閉ざされた瞬間、若者はキレて、無軌道な殺人を犯す。
『フェンス』では、黒人であることでメジャーリーガーへの夢を断念せざるを得なかった父親が、そのトラウマから、アメフトの才能を認められ進学して未来を切り開くことを懇願する息子にキレて、親子関係は破綻。1950年代、息子はやむなく軍隊へ入隊し、未来への可能性の扉を閉ざす。
オーガスト・ウィルソンの作品は「肌の色による差別」という現象が、ジェンダーや歴史、地理的要素など、さまざまな複合的な要素が幾重にも重なり合っている事実が浮き彫りにされる。水面下には、様々な文脈での「普遍的」な社会的問題が幾重にも絡み合っており、歪みの集合体の水面上の氷山の一角を指して、「人種差別」と呼称されているに過ぎない現実が透けてくる。
ピッツバーグと同じく、トランプ支持者が多いとされるラストベルトのエリアに属するイリノイ州ロックフォードを舞台に、スケボー仲間との10代の日常を記録した映画『行き止まりの世界に生まれて』」は、オーガスト・ウィルソン演劇の21世紀版ドキュメンタリーとも言えるかもしれない。
1989年生まれのアジア系移民のビン・リュー監督が自らカメラを回す定点観測の手法で制作されており、自らを含めそこに描かれる貧困の連鎖によるトラウマの世代間リレーの実態は、オーガストウィルソンの提示したテーマが、実は、人種差別の枠組みを越えた、現在進行形の「普遍性」をもったテーマであることを気づかせてくれる。
ジェンダーギャップが、世界ランキング120位で、G7のみならず、東アジアに限ってさえ最下位に近い日本。しかも、20世紀型の重工長大産業に依存してきた典型的な地方都市では、無数のトラウマが個人の魂にさまざまな疵を刻みつつある。その現実は、オーガスト・ウィルソンが描いたアメリカ社会とオーバラップして見える。
私も人口減少著しい日本の一地方都市で生活している中年男性である。それだけで、多くの局面においては「傷つける側」であるが、同時に「ジェンダーや年齢による役割が固定化されて自由度が少ない」というマチズモ溢れる保守的地域で育ったという面では、潜在意識下では、少なくない疵も抱えている。
今春、兵庫県豊岡市に劇団ごと移住され、「芸術文化観光専門職大学」初代学長として平田オリザさんが就任された。入学式挨拶は、マスコミやネット上でも話題になったが、翌日の新入生ガイダンスで語られた二つのメッセージも注目に値する。
一つは、さまざまな大人の期待を持って生まれた大学ではあるが、「大人の期待を鮮やかに裏切る」ことを若者の特権として行使するよう新入生に伝え、もう一つは、教師間も教師学生間もジェンダーを問わず呼称をすべて「さん」付けで統一すると伝えたことである。(岩波書店『世界』6月号)
どちらも何気ない普段着の言葉で語られており、とくにインパクトのないメッセージのように思えるが、実は、私は同じ日本の小さな地方都市に生きるものとして、この二つ、「ジェネレーションギャップ」と「ジェンダーギャップ」の克服がいかに実現の難しい命題であるかを肌で知っている。
「〜先生」「〜長」と社会的立場で互いを呼び合い、新聞やテレビ、ネットニュース以外、意識的に新しい情報に触れる努力をせず、親世代から受け継いだ価値観を疑うこともなく日々を過ごす人々が、知らず知らずのうちに内部の疵さえも受け継ぐ。
先頃、トランプ型の、事実に基づかない一方的なフェイクニュースの拡散される選挙によって、「演劇の街」を支えてきた中貝宗治さんが、豊岡市長の座を追われた。彼は、女性の地域からの流失を「女性たちの静かな反乱」と名言して、日本国内としては先進的なジェンダーギャップ解消に挑む行政の長として、全国から注目されていた。
世界は「差異」に溢れている。それらは、さまざまな個人の価値観の物差しを「多様性」と、個人の自由という「相対性」の名の下に放置されたままのように見える。果たして私たちは、お互いの「違い」を認める「多様性(Diversity)」と、同時に「違い」を乗り越える「普遍性(University))」を共有できるようになるのだろうか?
1987年生まれの若き哲学者、豊橋科学技術大学教授の岩内章太郎さんが先頃出版された『<普遍性>をつくる哲学:「幸福」と「自由」をいかに守るか』(NHKブックス)の結句を新たな世代の「希望」として、この稿の最期に紹介させて頂くことをお許しいただきたい。
自由への疲労を感じる者と自由から見放された者は、全く異なる理由から生の困難に直面する。そういう人びとにとって、〈普遍性〉という概念は、あまり重要なものには見えない。それは自由な生を楽しむことができる者の理屈であり、自分たちはそこから除外されているように思われるからだ。このリアリティは深いものである。
すると、普遍性を創出する動機が社会から奪われていく。しかし、その先にあるのは、暴力で自由を奪還しなければならないほどに、身動きが取れなくなった状態である。現象学的言語ゲームを開始して善の原始契約に入っていくことは、もう一度、自由の本質を自覚して、それを選び取ることを意味する。逆に言えば、大多数の人びとが自由を選ばない場合、現象学的言語ゲームは机上の空論にすぎない。
自由の普遍性は、その時代に生きる者のたゆまぬ努力が創出するものであって、あらかじめ世界に用意されているレディメイドではない。幸福の基礎条件としての自由の普遍性は、人間の努力によってのみ維持されるのだから。この努力を止めてしまえば、闘争状態に差し戻され、一人ひとりの生の選択肢は極端に狭くなってしまう。
それでも、人間は自由を選ぶ。私はそう信じている。
(岩内章太郎)