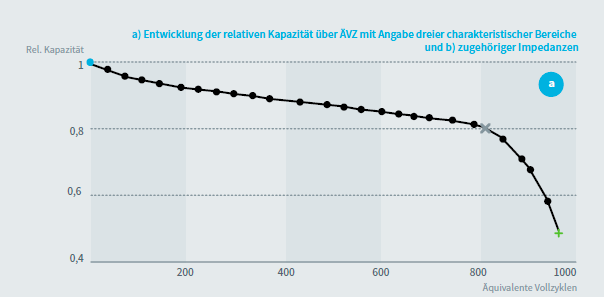パリ協定が世界の投資・金融の分野に与えるインパクトは非常に大きい。すでに世界各地で企業や金融機関が気候変動をビジネス上のリスクとして認識し、化石燃料からの投資撤退(ダイベストメント)をはじめている。さらに、企業に情報開示を求める動きや、国や企業の訴訟リスクも高まりつつある。
落胆と希望
2015年12月12日、2020年以降の気候変動対策の国際枠組みであるパリ協定が法的拘束力を持つ文書として採択された。確かに、複雑に入り組んだ対立点に関する長い交渉を経ての国際合意成立という意味では歴史的な出来事である。しかし、手放しで喜ぶことには少々違和感を覚える。なぜならパリ協定で法的拘束力を伴って規定された「産業革命以降の温度上昇を2℃あるいは1.5℃以内に抑制する」という目標達成への道のりは遠いからだ。
実際に、パリ協定の前と後で日本政府によるエネルギー・気候変動政策は変化しただろうか?答えは否である。日本における温暖化問題に関する政府審議会などでは、パリ合意の前に行っていた議論と全く同じような議論をパリ合意後も展開している。2016年2月8日、環境省は、石炭火力発電の新設を容認するよう方針転換した。現実的に考えて現与党政権が急激に政策変更する可能性は大きくない。
そうは言っても、パリ協定のビジネス、特に世界レベルでの金融や投資の分野へのインパクトは非常に大きいと思われる。実は、パリ協定には「低炭素発展経路に整合的な資金の流れを構築すべき」という一文がある(パリ合意第2条para.1a)。お金の流れは様々なリスクに敏感であり、大きなリスクのひとつとして気候変動や化石燃料がビジネスの世界で認識されたことの意義は大きい。
また、既得権益に影響されやすい行政や立法ではなく、司法の分野での展開も期待される。実は、パリCOP21の前から様々な気候変動関連の訴訟や裁判が世界中で起きており、パリ協定は、これらの動きを大きく加速すると予想される。
このような落胆と希望が交錯する状況の下、本稿ではパリ協定の国内外に与える影響について、特に化石燃料会社からのダイベストメント(divestment:投資撤退)、企業の情報開示、国や企業が持つ訴訟リスクの側面から考える。
ダイベストメント
ダイベストメントは2011年に米国の大学[1]から始まり、現在では、多くの企業、金融・保険機関、年金基金、投資家、地方自治体、財団、教会などが参加している。2015年12月時点で、このダイベストメントに賛同して参加している組織の数は世界中で500を超え、それらの保有資産合計額は3兆4000億ドル(約420兆円)に達する。この数字は、2014 年9月時点から比較すると70倍である[2]。下記は、主な賛同組織である。
- 政府年金基金:ノルウェー、スウェーデン、デンマーク、オランダ、カナダ、オーストラリア
- 州年金基金:米カリフォルニア州
- 保険会社:アクサ、アリアンツ、アビバ
- 大学:スタンフォード大学(米)、ジョージタウン大学(米)、カリフォルニア大学(米)、ハワイ大学(米)、オックスフォード(英)、グラスゴー大学(英)、シェフィールド大学(英)、ルンド大学(スウェーデン)
- 銀行:バンク・オブ・アメリカ、ING、シティ、クレディ・アグリコール、香港上海銀行
- 都市:オスロ、ストックホルム、アムステルダム、ベルリン、ロンドン、メルボルン、ウプサラ
- 財団:ロックフェラー財団
- 企業・業界団体:ガーディアン・メディア・グループ、英国医師会
- 教会:世界教会協議会、ルター派世界連盟、ヘッセ教会(ドイツ)、ナッソー教会(ドイツ)
ダイベストメントの影響の定量的な評価に関しては議論があるものの、このような動きの原因と結果の両方として化石燃料会社が持つ巨大な座礁資産問題や経営不振問題がある。座礁資産(Stranded Assets)とは、環境規制強化などにより将来使えなくなる石炭などの資産である。現在、世界経済の低迷とともにコモディティ市場価格が低迷しており、現実的に世界中の化石燃料会社の経営は急激に悪化している。資産価値が大きく減少しており、破産する企業も出ている。例えば、米国の4大石炭会社の市場価値は2015年の間に9割減少し、米最大手のArch石炭会社は2016年1月に、世界最大の石炭会社Peabody Energyは2016年4月に、それぞれ連邦裁判所に破産申請した。同じ1月には米格付け会社のムーディーズが120の石油ガス会社と55の石炭会社の格付けを下方修正し、シンクタンクのMercerは石炭関連産業の利益は今後35年間で18〜74%(GHG排出経路に依存する)減少すると予測している。監査法人のDeloitteも、2016年2月に世界の石油ガス会社の約3分の1が破産寸前にあるという報告書を出している。
ダイベストメントに関しては、カナダのシンクタンクであるCorporate Knightがその経済的な効果を定量的に評価するために「投資会社がもし仮に3年前に化石燃料会社からダイベストメントした場合の投資パフォーマンスの変化」を推定するプログラムを作っている。これによると、例えば全米でも有数の資産を持つゲーツ財団の場合、もしダイベストメントを実施していたら19億ドルの追加的な運用利益を得ていたとされる[3]。ケンブリッジ大学の持続可能な発展リーダーシップ研究所の研究も気候変動リスクの認識が株や債券などの投資ポートフォリオの価値を45%下落させる可能性があるとしている。実際に、2014年にカリフォルニアの年金ファンドは化石燃料会社に投資していたために50億ドル損失したとされる。
日本でもダイベストメントに関連した動きが見られるようになっている。例えば、350.org Japanという市民団体は、2016年2月11日、日本の銀行や保険会社による化石燃料会社や原発関連会社などへの具体的な投融資額を集計して公表した。これによると、東京三菱UFJ、みずほ、三井住友、三井住友信託を含む、日本のメガバンクグループによる2014年の化石燃料・国内石炭火力増設・原子力関連企業への投融資は合計で約5兆3892億円に上る。また、日本の大手生命保険会社は、化石燃料および原発関連企業へ3兆3300億円の投融資を行っていた。
一方、日本の銀行グループの化石燃料への投融資額に対し、再生可能エネルギーへの投融資額は約 8分の1の規模であった。350.org Japanは、2016年4月22日に「ダイベストメント声明」を発表し、日本の銀行、保険会社、年金基金や公的機関を含むすべての機関投資家に、化石燃料及び原発関連企業への投融資の停止・撤退、自然エネルギー開発への転換などを求めて署名活動を行っている。さらに、2016年4月14日、運用資産が100兆円を超える世界最大級の政府系ファンドであるノルウェー年金基金は、世界の石炭関連企業52社を基金の投資対象から外すと発表し、日本の投資先としては北海道電力、四国電力、沖縄電力の3社が除外された(朝日新聞2016年4月16日)。
ただし、投資における気候変動リスクに対する考慮の有無と投資パフォーマンスとの関係は単純ではない。現実的には、気候変動対策を目的としたダイベストメントがなくても、多くの投資資金が化石燃料関連からは撤退していたと考えられる。化石燃料会社の経営不振も、シェールガスや短期的な景気変動の影響によるものだという主張もある。米国のCompass Lexeconというシンクタンクは、ダイベストメントが投資家に対して追加的な取引コスト発生などによってマイナスの利益を与えるという報告書を出している[4]。この報告によると、南アフリカでのアパルトヘイト反対の際に発生したダイベストメントの際も、投資撤退が南アフリカの経済自体に大きな影響を与えなかった。さらに、ダイベストするのではなくて、アクティビスト投資家(物言う株主)となって経営などに直接的な影響力が持った方が良いという議論もある。
このようにダイベストメントの効果や影響に関しては様々な議論があり、現時点で単純な評価を下すのは注意が必要である。ただし、ダイベストメントの影響は経済的なものだけで測れるものではなく、まさにアパルトヘイト反対運動のように社会意識醸成や国内外での法律制定への影響など多層的かつ長期的な意味を持つ。もちろん株主への直接的・間接的な影響もある。今後は、そのような広角的な視点からの深い分析が期待される。また、単なるダイベストメントではなく、撤退した資金を再生可能エネルギーや省エネの導入に投資(Investment)するようになれば、すなわち「ダイベストメント & インベストメント」という動きが加速すれば、低炭素社会に変革するための役割としての評価はより高まると思われる。
企業の情報開示
金融安定理事会タスクフォース
現在、気候変動が金融システム全体の不安定性を増大させることに対する懸念も高まっている。このような懸念を象徴するものとして、主要25か国・地域の中央銀行、金融監督当局、財務省などの代表が参加する金融安定理事会(Financial Stability Board: FSB)[5]の動きがある。
イギリスの中央銀行であるイングランド銀行の総裁で金融安定理事会の議長でもあるマーク・カーニーは、G20財務相会議からの要請という形で世界の金融システムが持つ気候変動関連リスクの現状把握、ストレス・テスト実施のためのシナリオや指標の作成、開示すべき具体的な情報の特定、リスク削減策の提言などを目的とするタスクフォース(Task Force on Climate-related Financial Disclosure : TCFD)をCOP21の場で立ち上げた。そのタスクフォースのヘッドとしてマイケル・ブルームバーク元ニューヨーク市長が指名された。
タスクフォースの主要目的は、(1)基本原則を決め、効率的かつ効果的な気候関連のディスクロージャーを推進する、(2)投資、融資、保険引き受けの判断が気候関連財務に関して十分な情報に基づいて行われることを推進する、(3)金融セクターにおける炭素関連資産の集中、および金融システムの気候関連リスクへのエクスポージャーに関する様々なステークホルダーの理解を深めるなどである。最終レポートでは、気候関連財務報告の一貫性、アクセスのしやすさ、明確性、有用性を高めるための先端的な取り組み事例を識別し、任意的ディスクロージャーに関わる具体的なガイドラインなどに関する提言を行うことである。
マーク・カーニーは、金融・投資という側面から、気候変動リスクには、(1)物理的リスク、(2)産業変革リスク、(3)訴訟リスクの3つがあると様々な場で発言している。1番目の物理的リスクは、たとえば洪水や海面上昇などによって資産が毀損するリスクである。2番目の産業変革リスクは、新たな法制度などの導入の影響によって市場を通したモノとサービスの動きが変化するリスクである。第3は、企業や政府が温暖化問題に関する不法行為によって訴訟の対象となるリスクである。
これまでの企業による気候変動に関する情報開示や指標は、炭素排出原単位など限られたものであり、上記の3つのリスクに直接的に関係しないものがほとんどであった。したがって、タスクフォースの特に重要な役割として、現在議論されているストレス・テスト[6]を実施する場合の具体的なシナリオ[7]の策定や、気候変動リスクをより正確に示す一貫性のある指標作り、データ収集などがある。
フランス・エネルギー転換法
2015年7月、フランスで画期的な「エネルギー転換法」が制定された。その173条では、気候変動に関連してフランスの企業、銀行、機関投資家などに対して年次報告書での詳細な情報開示を求めている。
具体的には、企業(銀行を含む)に対しては、「気候変動関連の金融リスクおよびその緩和策、自社のビジネスに関連した温室効果ガス(GHG)排出量(例:自社および投資先のバリュー・チェーン全体でのカーボン・フットプリント)、気候変動リスクに対する脆弱性(例:前述の3つの気候変動リスクに対して自社の経営戦略や投資ポートフォリオが持つ脆弱性評価や温暖化によって影響を受ける具体的な資産額)、自らの企業活動が気候変動に与える影響」、銀行に対しては「気候変動がバランス・シートに与える影響、ストレス・テストの実施結果」、機関投資家に対しては「保有資産のGHG排出量、今後の投資計画が持つ気候変動リスクの大きさおよび国・地域・世界のGHG排出削減目標などとの整合性」などに関する情報の開示などをそれぞれ要求する。
これは、いわば企業の事業計画や機関投資家のポートフォリオがフランスの数値目標だけでなく世界全体の目標、すなわちパリ協定で法的拘束力がある目標として規定された2℃目標や1.5℃目標などとの整合性を持つべきことを事実上要求している。
訴訟リスク
前述のFSB議長が提示した3つの気候変動リスクのうち、特に注目されるのが訴訟リスクである。なぜなら、どの国でも多かれ少なかれ化石燃料会社やエネルギー多消費産業が政権の支持基盤となっているため、政策の急激な変更、すなわち野心的な省エネや再生可能エネルギーの導入を立法や行政に期待するは現実的には難しいからである。
しかし、三権分立が確立している民主国家であれば、司法が政府や企業を動かすことができる。国や企業が他国の政府や企業を訴えることも原理的には可能である。特に、企業は、裁判という形で法的責任を訴追される可能性があるだけでも大きなリスクとして認識する。すなわち、短期的利益を追求するがゆえに、実際の経営や投資パフォーマンスに影響する可能性がある場合、リスク回避に敏感な企業は政府の対策や取り組みとは段違いのスピードで対応せざると得なくなる。
振り返って見れば、かつての日本の公害問題においても訴訟の役割は極めて重要であった。また、気候変動の被害が顕著になり、ある程度は因果関係が論理的に挙証できるような段階までに気候変動問題が「成熟」したとも言える[8]。
以下では、このような訴訟リスクに関して、国が被告になる場合と企業が被告になる場合の二つについて説明する。
国が被告になる場合
実際に国が被告となった例としては、最近ではオランダの市民団体である Urgendaが「オランダ政府はより野心的なGHG排出削減数値目標を持つべき」と訴えた裁判がある[9]。この裁判では、2015年6月にオランダ・ハーグ地方裁判所が「オランダ政府はGHG排出削減を積極的に進めなければならない。具体的には2020年までに1990年比で25%削減する必要がある」という判決を下した。すなわち、市民団体側が勝訴し、現在、オランダ政府は上訴検討中である。同様の裁判はパキスタンでもあり、市民団体側が一審では勝っている。ベルギーやノルウェーなどでも同様の裁判を市民団体が準備中である。
オランダでの判決で特に注目されるのは、「メキシコ・カンクンでのCOP20宣言に同意した国は2℃目標にコミットしているのだから公平性に基づいた排出削減に関する行動を取る必要がある」と2℃目標を各国政府が順守すべき目標として明確に位置づけたことである。また、「気候変動に関する政府間パネル(IPCC)の450ppmシナリオに基づいて、先進国は2020年までに1990年比で25〜45%削減する必要がある」と、科学的に信頼性のあるものとしてIPCCの第4次報告書(AR4)の数字に全面的に依拠している。
さらに、「IPCCは公平な分担方法について複数の公平性に関する指標から検討し、その結果が25〜45%という幅のあるものになった」と判決文では説明している。すなわち、特定の公平性指標が正しいとするのではなく、様々な公平性指標を用いて計算した結果の「先進国が義務として順守すべき排出削減必要量の幅」を重要な指標として示している。
「予防原則」に基づいて、削減義務や早期行動の必要性も正当化していることも興味深い。なぜなら、これまでは「科学的不確実性は行動しないことの理由にはならない」という文脈やロジックのみで予防原則は使われていたからである。
オランダ政府(の弁護人)は「オランダの排出量は世界の0.5%に過ぎない」とも主張した。これは「1%問題」とも呼ばれており、似たようなロジックはどこの国でも聞かれる。しかし判決は、「各国は、共同および単独での排出の責任がある」「他の国に比べての排出量の多寡は、予防原則のもとに各国が持つ削減義務や責任には関係しない」「一人当たりの排出量の大きさや先進国であることを鑑みれば、オランダはより積極的な削減をする必要がある」としてこの主張の正当性を否定した。
企業が被告になる場合
(1)米国RICO法違反
“Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act(ゆすり、たかり、脅迫行為による影響を受けた組織及び腐敗した組織に関する法律:通称RICO 法)”は、1970年に当時の米国のリチャード・ニクソン政権において制定された組織犯罪対策法を含めたマフィアなどを取り締まる組織犯罪取締立法の一環として成立した。
このRICO 法がタバコ会社訴訟に適用されてタバコ会社が敗訴した例としては2010年の連邦最高裁での判決がある[10]。その判決に基づいて2014年には、米フロリダ州の陪審団が米大手タバコ会社RJレイノルズに対して約236億ドル(約2兆3900億円)の支払いを命じる評決を言い渡した。この2014年の裁判では、あわせて、喫煙者の遺族側に対する約1700万ドル(約17億円)の損害賠償も認められた。
米国では、1950年代から90年代前半頃までは、同様の裁判ではタバコ会社側がほぼ全て勝訴していた。しかし、1990年代後半頃から、内部告発や内部文書により、タバコ会社が健康被害や依存性について熟知しながら、それを隠して、故意に詐欺的な販売を継続してきたということが明らかとなって潮目が変わった。この結果、50の州政府が原告となって公的医療費の返還を求めてタバコ会社を訴えた裁判では、1998年に2060億ドル(約25兆円)を25年間分割払いにする和解が成立している。また、喫煙者個人やその遺族がタバコ会社を訴えた裁判は、2000年代以降、次々と勝訴し、約5億円、9億円、50億円、79億円といった懲罰的賠償も認められている(弁護士ドットコムニュース2014年8月11日)。
現在、このような「企業が内部告発や内部文書により、健康被害や依存性について熟知しながら、それを隠して、故意に詐欺的な販売を継続してきた」という嫌疑は、まさに化石燃料会社にかけられている。それは、2015年9月16日付けのInside Climate Newsという米国の新聞社による「Exxon: Road not taken(エクソン:通らなかった道)」というタイトルの調査報道記事がきっかけとなった。
記事の内容は、「米国のExxon Mobil社において社内の研究者が1970年代から化石燃料使用による負の影響を幹部に知らせていた。しかし、幹部はそれを公表しなかったばかりでなく、逆に社会に対しては温暖化を否定するような温暖化懐疑論を意図的に広めていた」という事実を明らかにしたのもので、米国では一種のスキャンダルになっている。多くの環境団体と共に民主党大統領候補のサンダース上院議員とクリントン前国務長官の両方とも、Exxon Mobilに対してはRICO法に基づいて法的な責任を問うことを司法当局に求めており、2016年2月、米連邦司法当局は米国下院議員3人による調査要請を米連邦捜査局(FBI)犯罪調査部門に報告して判断を求めた。現在、同じ下院議員がShellに対しても同様の調査を証券取引委員会に求めている。
(2)ニューヨーク州マーチン法違反
現在、Exxon Mobilは、前出の米国連邦法であるRICO法だけではなく、ニューヨーク州司法当局から企業の不法行為から消費者を保護するために作られたマーチン法(1921年制定)に違反した可能性についても調査されている。このニューヨーク州独自の法律であるマーチン法は、全米レベルの法律であるRICO法と同じように、企業が故意に誤った情報を提示することを罰する法律である。もし企業の違反が明白になれば、州当局が課徴金などを要求する可能性がある。実際に、これまで多くの企業の不法行為が摘発されており、最近では世界最大の石炭会社であるPeabody Energyが捜査対象となっている。その結果、2015年11月に2年越しの調査と交渉を経て市当局とPeabody Energyの間でさらなる情報公開の義務づけなどの内容の和解が成立した(なお前述のように、2016年4月、Peabody Energyは米連邦裁判所に破産申請した)。
このマーチン法は、投資側の不法行為についても対象とする。すなわち、機関投資家、特に長期的観点から投資する義務がある年金運用会社(運用額は株式市場総額の25%を占める)などが気候変動のリスク管理を怠った場合は職務上の受託者義務違反となる可能性がある(Covington et al. 2016)。これは、投資先を検討する際に気候変動被害の観点が必要不可欠となることを意味している。
前述のように、実際には投資パフォーマンスの要因分析は難しい。しかし、少なくとも、気候変動リスクに対して、より細かい情報開示や説明が法的拘束力を持つ義務として求められ、2℃目標あるいは1.5℃目標の達成という前提のもと、その内容に対して株主などの投資家だけでなく国、企業、市民団体、そして裁判所までが意見・命令する時代になったと言える。
今後の展望
今後の展開においては以下のような点が重要なポイントとなると思われる。
フランス・エネルギー転換法およびFSBタスクフォース勧告の具体的な内容
フランスのエネルギー転換法は、現在、企業が実施すべきストレス・テストの内容などの細かい法令の作成段階にある。一方、FSBタスクフォースは、2016年2月にタスクフォースのメンバーが発表されて、銀行や保険業界の実務家(プライベート・セクター)からなる構成になった。2016 年3月31日には第1フェーズ報告書が発表され、2017年3月に最終報告書が発表される予定である。どちらも詳細はこれからであり、すでにシンクタンクなどが中身に関する具体的な提案をしている。
この情報開示に関する2つの新しい規制(フランスの場合は義務、FSBの場合は自主規制)の導入によって、これまでのSRI(社会的責任投資)やESG(環境、社会、企業統治)投資のレベルを超えた対応が国や企業に求められ、その影響範囲は企業のバランス・シートと利益損失の両方に及ぶと思われる。影響を受ける分野も銀行・保険業界に限らないだろう。
ただし、気候変動リスクが長期的なリスクであることの認識は必要である。まさに前出のイングランド銀行総裁のマーク・カーニーが “Tragedy of Horizon” と呼ぶように、気候変動問題の解決が難しい大きな理由のひとつは、対策は短期的でも被害は長期的なものという時間差が存在するからである。その意味で、金融・投資の世界に住む大多数のプレーヤーにとって、気候変動リスクが(いわゆる金融業界で使われる狭義の意味での)“Systemic risk”となって、リーマン・ショックのように金融不安定化を短期間でもたらすとは現実的には考えにくい。まだ多くの投資家にとっては、せいぜい数年単位でしか重要なリスク(Material risk)は存在しない、あるいは長期的なリスクはそれほど考えなくてよいという認識があるからである。
だからこそ、炭素税や排出量取引制度による炭素価格付けやシャドウ・プライス[11]の導入など、全てのステークホルダーが長期的な時間軸を考慮せざるを得ないような制度設計が必要とされる。
「損失と被害」に関する国際交渉の進展
パリCOP21交渉では、「損害と被害」条項が極めて大きな争点であった。具体的には、(1)パリ合意の中に「適応」に関する条項とは異なる独立した条項として「損害と被害」を入れるか否か、(2)気候変動難民保護などに関する新たな組織を作るか否か、などで米国を中心とする先進国と脆弱国を中心とする途上国が対立した。最終的には、まず先進国側が「損害と被害」を独立した条項とすることを認めた。一方、途上国側は、(1)パリ合意の中に「「損失と被害」条項は「責任と賠償」の議論につながらない」という一文を入れる[12]、(2)「損失と被害」の具体的な制度設計に関してはワルシャワ国際メカニズム(Warsaw International Mechanism)という既存の組織を活用する、という先進国側の要求を受け入れた。すなわち、痛み分けと言いうる結果であった。
しかし、これで気候変動を巡る「責任と賠償」の議論が終結するとは到底考えられない。すなわち、UNFCCCの内外で、温暖化の被害者が加害者の法的責任を問う訴訟活動などを通して「責任と賠償」の具体化や制度化の要求はより強まると予想される。
実は、脆弱国が1.5℃目標に拘った理由の一つとして、今後の「損失と被害」に関する交渉を有利にすることもあると推察される。なぜならば、1.5℃が目標である場合、2℃目標だけの場合と比べてBAUシナリオ(人為的な温暖化が存在しない場合)との差で考えた被害者数の数が大きくなるからである。これは、いわゆる「責任と賠償」を被害者として問う「原告」の数が多くなり、その主張の正当性もより強くなることを意味する。
なお、気候変動における「損失と被害」の制度化に関しては、日本とも関わりがある「仙台防災枠組み(Sendai Framework for Disaster Risk Reduction)」との関係も重要なポイントになる。
ニューヨーク州司法当局などのExxon Mobilへの判断(懲罰的賠償金の有無)
この調査に関しては、ニューヨーク州と同様の法律を持つメリーランド州など7つの州<[13]の司法長官が参加することになった(Inside Climate News 2016 年3月30日)。また、バージン・アイランド州の司法長官はCompetitive Enterprise Instituteという保守系シンクタンクに対してExxon Mobilからの献金で温暖化懐疑論を広めたという容疑で召喚状を出している(Inside Climate News 2016 年4月8日)。
このような捜査が進行し、もし米司法当局がタバコ会社に対して決定したような多額の懲罰的賠償金を要求することになれば、化石燃料会社にとっての経済的・社会的なダメージは非常に大きなものになるだろう。また、気候変動がもたらすリスクの問題構造はアスベスト被害や土壌汚染の問題構造とも似ており、多くの場合に企業に変わって賠償金や保険金を支払うことになる保険会社などへの影響も大きくなると予想される。いずれにしろ、様々な事実が明るみに出てくれば、責任や補償の議論は避けられず、Exxon MobilやShell以外の企業への同様な訴訟が続き、そのダメージは化石燃料会社だけでなく他の分野にも影響すると思われる。
各国での訴訟の活発化(法律制定、集団訴訟)
前述のオランダでの裁判のロジックは普遍化できる可能性があり、すでに様々なシンクタンクや法学者が具体的な法案のひな形を出している。例えば、バヌアツの環境法研究者などがCOP21直前に「A Model Climate Compensation Act(気候賠償モデル法)」を発表している。これは法的手続きに関する詳細な解説を含んでおり、いわば気候変動の被害者が加害者の法的責任を追求する場合の「訴訟マニュアル」のようなものだと言える。
また、コロンビア大学のロースクールの中にある気候変動法研究センター教授で気候変動に関する裁判を専門とする Michael Gerrard は、気候変動の被害者が加害者である企業や国を訴える場合、(1)米国ではこれまでは連邦公害訴訟法に基づいた訴訟がほとんどであり、多くが却下された、(2)しかし、各州の公害訴訟法に基づいた場合は却下されるかわからない(まだ試されていない)、(3)国際司法裁判所に訴えるよりも、各国がまず国内法を整備して、それに基づいて自国の裁判所で他国の企業や政府を訴える方が原告勝訴の可能性が高い、とコメントしている。
2016年3月9日、米国オレゴン州でオランダでの裁判と同じような政府および化石燃料会社の不法行為を訴える裁判が起こされている。すでに温暖化の被害を受けたという若者たちによるものであり、(1)米国憲法で保証されている年少者が年長者と同じ保護を受ける権利、(2)同じく米国憲法にある政府の環境保護実施義務(公共信託原理)、の2つに基づいて提訴している。今後は、様々な場所で様々な訴訟が起こされ、集団訴訟なども実施されると予想される。
結びにかえて
パリ協定の誕生は京都議定書の死を意味する。その意味で、パリ協定の誕生は、日本人としても環境問題の研究者としても寂しさと無力感の両方を感じる。また、冒頭でも述べたように、日本の政策策定の現場においては、パリCOP21合意の前に行っていた議論や政策と同じような議論が展開され、同じような政策が実施されている。そもそも、日本のエネルギー政策や政治経済社会システムをパリ協定が簡単に変えられると考えること自体に無理があるのだろう。
ただし、仮に京都議定書のように法的拘束力や制裁措置がある仕組みを西洋薬に例えれば、ゆっくり確実に効果をもたらす可能性があるパリ協定は漢方薬に例えられる。すなわち、2℃/1.5℃目標達成という絶対的な前提のもと、本稿で述べたような一見バラバラのように見える動きが有機的に結びついて、今後は国際社会において法的責任や賠償、そして情報開示に対する議論が高まり、リスク回避に敏感なビジネス社会での資金の流れが変化することは十分に考えられる。そのような変化が国際社会で「ニュー・ノーマル」になれば、それは政治経済社会システム全体が変化、いわば体質改善を果たしたことになる。もちろん、それは日本にもあてはまる。
そうは言っても、それらはあくまでも2℃あるいは1.5℃目標達成のための必要条件であって十分条件ではない。日本をはじめ各国政府が2℃目標達成に十分なGHG排出削減の実現するような政策を実施するようになるためには、パリ協定という漢方薬だけでは不十分であることは明白である。すなわち、様々な側面からの市民社会による途方もない努力・抵抗そして温暖化被害の甚大化も必要とされる。それが冷徹な現実であり、覚悟でもある。
謝辞:本稿を作成するにあたり、京都大学大学院総合生存学館の河合(石田)江理子教授に多くの知識や示唆を頂いた。ここに感謝の意を表する。
註
[1] 米国のスワースモア大学から始まった。日本でも350.org Japanという市民団体がダイベストメントに関わる活動を行っている。 [2] すべての組織が化石燃料関連の株や債権を100%売却したとは限らない(一部のみの組織も存在する)。 [3] ゲーツ財団はダイベストメントに賛同していないために試算対象となった。 [4] 追加的な取引コストの発生などを理由としている。 [5] 金融安定理事会はバーゼルにある国際機関。1999年に設立された金融安定化フォーラム(Financial Stability Forum: FSF)を前身とし、FSFを強化・拡大するかたちで2009年4月に設立された。金融システムの脆弱性への対応や金融システムの安定を担う当局間の協調の促進に向けた活動などが行われている(日本銀行HPより)。 [6] Financial Stability Board 2016, “Task Force Phase I Report” Task Force on Climate-related Financial Disclosures FSB, 1 April 2016, 27ページ. [7] 具体的には、気候変動激化のレベルや緩和・適応のための様々な制度導入の有無で差異化したシナリオを策定する必要がある。 [8] 例えば熱波の発生に関する人為的な影響は、干ばつや台風の発生に関する人為的な影響に比較して定量的により明らかになりつつある。National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine(2016)などを参照のこと。 [9]この裁判の意義などに関しては、Brown(2015)が詳しい。 [10] この背景には2006年にワシントン地方裁判所で政府がタバコ会社をRICO法で提訴して政府が勝訴した判決がある。 [11] 米国政府は、2010 年から炭素のシャドウ・プライス(社会的費用)を考慮して法律や規制を策定しており、2010 年時点では19 ドル/ t-CO2、2015 年2 月時点では37 ドル/t-CO2をそれぞれ使っている(例えば、2010 年のオバマ大統領による自動車の燃費基準の制定の際は19 ドル/t-CO2)。また米国企業も、最近では、この程度の社会的費用としての炭素価格を自社の投資判断に実際に使っている。例えば、BP は40ドル/t-CO2、Exxon Mobil は60ドル/t-CO2、Shell は40ドル/t-CO2、Google は14ドル/t-CO2をそれぞれ用いている(CDP North America 2013)。 [12] “The Conference of the Parties agrees that Article 8 of the Agreement does not involve or provide a basis for any liability or compensation”という一文がパリ合意の第51パラグラフに入った。 [13] 7つの州は、それぞれニューヨーク州、バーモント州、バージニア州、マサチューセッツ州、メリーランド州、コネチカット州、バージン・アイランド州。参考文献
Brown Donald 2015, The Enormous Significance For Climate Law and Ethics Of a Dutch Court’s Order Requiring the Netherlands To Reduce Its GHG Emissions by 25% by 2020, Ethics and Climate.
CDP North America 2013, Use of internal carbon price by companies as incentive and strategic planningtool December 2013, A white paper from CDP North America A review of findings from CDP 2013 disclosure
Covington H, Thornton J, Hepburn C. 2016, Shareholders must vote for climate –change mitigation, Nature, Vol.530, 11 Feb. 2016.
National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine 2016, Attribution of Extreme Weather Events in the Context of Climate Change