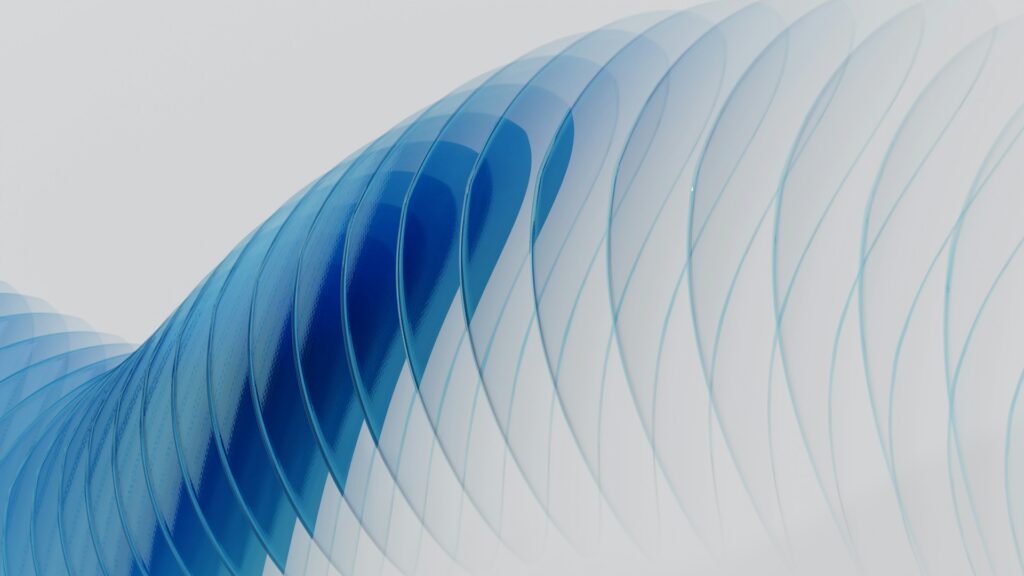国際司法裁判所は2025年7月、気候変動に関する国家の義務と義務違反の法的帰結を示す勧告的意見を公表した。本稿は、この勧告的意見が日本のエネルギー・温暖化政策と気候訴訟に与える具体的影響を、NDCの設定、化石燃料補助金、原告適格、損失と被害の賠償可能性などの論点から整理する。
はじめに
2025年7月23日、オランダ・ハーグにある国際司法裁判所(International Court of Justice, ICJ)は、気候変動に関する国家の義務および義務違反の法的帰結に関する勧告的意見(以下、ICJ勧告的意見)を発表した1 ICJ(2025)Obligations of States in respect of Climate Change – The Court gives its Advisory Opinion and responds to the questions posed by the General Assembly, July 23, 2025. 。このICJ勧告的意見は、ハーグを舞台に、各国政府関係者、世界中の法学者、市民社会が活発に関与した2年間にわたるプロセスの集大成であり、発表の場には国連総会議長や各国代表が出席し、世界各都市でライブ配信された。
多くの市民団体や法律家グループは、「気候変動問題のすべてを変えるゲーム・チェンジャー」などの表現できわめて好意的に受け止めている。前UNFCCC事務局長クリスティナ・フィゲーレスは、「もう気候変動枠組条約(UNFCCC)締約国会議(COP)での新たな協定などは必要ないのでは?」とすら述べている2 Optimism and outrageous (2025) Planetary News: The ICJ Climate Opinion Explained, July 25, 2025. 。

ICJ勧告的意見が生まれたきっかけは、約5年前に南太平洋大学の27人の学生がはじめたキャンペーンである。それを小島嶼国であるバヌアツ共和国がとりあげ、国連の場での協議を経て、2023年3月29日に、国連総会が下記の2つの質問に対する答えとなる勧告的意見の発出をICJに要求する決議を全会一致で採択した。
質問1:国際法上、国家が持つ、気候システムおよびその他の部分を含む環境を、人類の現在世代および将来世代のために温室効果ガスの人為的排出から保護する義務とは何か?
質問2:これらの義務に違反し、その行為または不作為により気候システムおよび環境の他の部分に対して重大な損害を与えた国家に対する法的帰結、特に 地理的状況や開発水準のため、気候変動の有害な影響により被害を受けたり、特別に影響を受けたり、または特に脆弱な立場にある小島嶼開発途上国(SIDS)を含む国家および気候変動の有害な影響を受ける現在および将来世代の人民および個人に対する法的帰結は何か?
その後、日本政府を含む各国および国際機関から91件の陳述書ならびに62件の書面コメントがICJに提出された。また、2024年12月2日から13日まで口頭審理が開催され、96カ国および11の国際機関が口頭陳述をおこなった。
このICJ勧告的意見に関しては、すでに国立環境研究所の久保田泉氏が内容全般に関する紹介記事を書いている3 久保田泉(2025)法の支配に基づく新たな気候変動対策時代の幕開け—国際司法裁判所の勧告的意見を読み解く, 研究コラム, 国立環境研究所, 2025年8月8日. 。したがって、本稿では、「日本政府のエネルギー・温暖化政策」「日本での気候訴訟」の2つへの影響にフォーカスして具体的なポイントを紹介する。
まず、ICJ勧告的意見で否定された日本政府の主張を個別に挙げて、ICJ勧告的意見と対比させる。次にそれらを踏まえて、日本でのエネルギー・温暖化政策および気候訴訟への影響について、今年2月に閣議決定した第7次エネルギー基本計画での議論や日本での気候訴訟の判決を振り返りながら解説する。加えて、その他の重要論点について述べる。最後に全体をまとめる。

ICJ勧告的意見によって否定された日本政府などの主張
ここでは、ICJに対する日本政府の陳述および日本での気候訴訟における判決などから、今回のICJ勧告的意見によって否定された日本政府の主張や気候訴訟の判決を整理し、その背景などを考察する。
日本政府などの主張 1
国家は気候変動条約で合意した任意の義務しか負わない
日本政府も含め、大量排出国は、「国家は気候変動枠組条約(UNFCCC)およびパリ協定で合意した任意の義務しか負わない」と主張した。しかし、UNFCCCの目標は曖昧で、パリ協定の目標は各国の任意で、かつ目標遵守は法的拘束力がない。
そのため、ICJ勧告的意見は、すべての国は、既存の条約・協定の内容や参加の有無(米国はパリ協定から脱退)に関係なく、国際法において包括的・統合的(アンブレラ的)な役割を担う習慣国際法上の義務として、気候システムの保護義務を負うとした。
ちなみに、下記は日本の外務省HPにある「慣習国際法」の説明である。
「法というと、通常は文書になっているものを連想しがちですが、国際法では、「国際慣習法(注)」という文書化されていない法が重要な地位を占めています。国際社会においては、国内の議会のような立法機関はなく、国際法の拘束力は国家間の合意によりますが、一定の行為について、国際的な慣行(一般慣行)が多数の国によって法的に義務的又は正当なものとして認められる(法的確信)ときには、国際慣習法が成立し、国際社会のすべての国家を拘束します。」4 外務省(2003)国際法あれこれ, 外務省HP.
(筆者注:「国際慣習法」は「慣習国際法」と呼ばれる場合がより一般的なので、本稿では慣習国際法と記述する)
なお、具体的な慣習国際法としては、「他国に対するDo No Harm (害悪を及ぼさない)ルール」などがある。
日本政府などの主張 2
国が定めるNDC(国が決定する貢献)のレベル(野心度)に関して国家は裁量権を有する
ICJ勧告的意見は、このような国の裁量権を完全否定した。また、ICJ勧告的意見は、NDC設定について、共通だが差異のある責任と能力(CBDR-RC)の原則のもと、蓄積排出量(歴史的排出量)などの具体的な指標を示した(詳細は後述)。
日本政府などの主張 3
国家に温室効果ガスの歴史的排出責任はない
日本政府は、ICJへ提出した意見において、「気候変動対策における先進国の先導的役割は認識するが、国際法上、義務の遡及適用はなく、歴史的責任は生じない。」5 地球規模課題審議官組織 国際法局(2024)気候変動に係る諸国の義務に関するICJ勧告的意見手続:口頭陳述, 2024年12月. としていた。
一方、ICJ勧告的意見は。国がもつ温室効果ガスの排出責任に関しては、蓄積的・歴史的排出を考慮すべきとした。
日本政府などの主張 4
国家が温室効果ガス(GHG)排出から気候システムを保護するための適切な措置を講じないことの法的帰結はない
ICJ勧告的意見は、化石燃料の生産、消費、化石燃料探査許可の付与、化石燃料への補助金提供などが、その国家に帰属する国際法上の不法行為を構成するときわめて具体的に明記した。すなわち、化石燃料使用などを具体的な不法行為と定義した。
日本政府などの主張 5
気候変動の責任問題において、被害と加害の因果関係(causation)および帰属性(attribution)を明らかにすることはできない
大量排出国は、気候変動被害と温室効果ガス排出の因果関係および帰属性を明確化するのは困難と主張してきた(日本での気候訴訟における国・企業などの被告の主張も同じ)。
しかし、ICJ勧告的意見は、気候変動被害と温室効果ガス排出の因果関係を明らかにするのは科学的に可能とした。
日本政府などの主張 6
清潔で健康的で持続可能な環境を享受するという人権はなく、他の基本的人権の享受とも関係ない
日本の裁判所は、「気候変動による健康、生活の質等に対する重大な悪影響から保護される権利」の存在や「清浄で健全かつ持続可能な環境を享受する権利」の存在を明確にしていなかった。すなわち、「気候変動の被害は人権侵害で人権法違反」という主張は、これまでの日本での気候訴訟では裁判官に無視されてきた。
一方、ICJ勧告的意見は、明確に気候変動問題は人権侵害問題とした。
日本政府の主張 7
ICJ勧告的意見は、気候危機という文脈において、被害を受けている国々が大排出国に対して行動の停止、回復(原状回復)、損害賠償を求めることはできない
日本政府は、「パリ協定における損害に関する規定は、第8条(気候変動の悪影響に伴う損失及び損害(loss and damage)の回避、最小限化及び対処)であるが、第8条の実施は協力的な性質であり、2015年のCOP21において、第8条は「いかなる責任や補償も伴うものではなく、その根拠となるものではない」との決定を採択している」などを主張していた6 Government of Japan(2024)Obligations of States in Respect of Climate Change (Request for Advisory Opinion), Written Statement of the Government of Japan, 22 March 2024.。
一方、ICJ勧告的意見は、パリ協定のみならず慣習国際法などの見地からも賠償などを求めることは可能とした。

日本のエネルギー・温暖化政策および気候訴訟に対する影響
ここでは、上記を踏まえて、エネルギーや温暖化対策に関する現在の日本の行政および司法に対する具体的な影響について深掘りする。
温室効果ガス排出削減数値目標(NDC)
各国数値目標の1.5℃目標整合性問題は、実質的にはカーボンバジェットの分配問題と言い得る。これまで日本政府は、カーボン・バジェットの分配に関する国際的な指標やルールは存在せず、NDCは国家の裁量で勝手に決められると主張してきた。
しかし、ICJ勧告的意見は、国家に裁量権はなく、かつ分配の指標として、共通だが差異のある責任と能力(CBDR-RC)、公平性(equity)、蓄積排出量、歴史的排出量、一人あたり排出量、発展段階、予防原則などを考慮するべきとした。
具体的に日本の文脈で述べると、2024年後半から2025年年初にかけての日本のNDC(2035年における2013年比での温室効果ガス排出削減数値目標)策定プロセスにおいて、日本政府は3つの温室効果ガス排出経路を提示し、いずれも1.5度目標にそっていると主張した。
一部の審議会委員は、その根拠として世界全体のカーボンバジェットを「限界削減コスト均等」で日本に分配すると1.5度目標にそっていることになると主張した。
ICJ勧告的意見によって、これらの主張はすべて否定あるいは無効化されたことになる。
化石燃料補助金
日本政府は、「電力の供給力の確保」のための仕組みとして、容量市場や長期脱炭素電源オークションと呼ばれる制度を導入している。しかし、これらの制度によって大規模火力電源へ多額の補助金が渡っており、日本政府は、実質的に化石燃料発電維持政策をとっていると言える7 工藤美香(2025)長期脱炭素電源オークションの有効性を問う, シリーズ「長期脱炭素電源オークションの課題」第1回総論, 連載コラム, 自然エネルギー財団, 2025年7月16日. 。
IEAが「1.5℃目標達成には、先進国は2035年までに化石燃料発電を廃止する必要がある」とするなか、ICJ勧告的意見は、化石燃料発電への補助金などを国際的な不法行為と位置付けた。これは日本政府が実施している上記政策などの不法行為性が明示的に示されたことを意味する。
気候訴訟における原告適格
日本での気候訴訟において、国や企業を相手取った原告は、「人が安定した気候を享受する権利は人権であり、それが侵害された場合は人権侵害にあたる」と主張してきた。
しかし、日本の裁判所はこのような考え方を否定し、気候変動による被害を人権侵害と認めず、ゆえに原告適格も認めなかった8 気候ネットワーク(2024)世界に広がる気候訴訟 気候変動問題を解決する:司法を通じた道筋, 2024年8月. 。それどころか、日本では、環境保全の利益を守るために、環境団体等が裁判を起こすことも認められていない。
実際に、筆者がかかわった仙台での石炭火力発電所差止訴訟(2017年9月27日提訴)では、裁判長によって、地球温暖化問題は最初から争点から外され、大気汚染問題のみが争点となった。
しかし、今回のICJ勧告的意見は、気候変動の被害を受けることは人権侵害であり、「清潔で健康的で持続可能な環境への権利」が、基本的人権を実効的に享受するための不可欠な前提として、気候変動の被害を受けない権利を他の基本的人権とも結びつけた。
したがって、今後は気候訴訟において原告不適格という判断を裁判官が下すのは困難になると思われる。また、ICJ勧告的意見は、前述のように責任不履行や不法行為の法的帰結として、賠償の可能性についても示した。これは、国や企業への賠償請求訴訟だけでなく、COPなどでの「損失と被害(loss and damage)」に関する国際交渉の議論にも影響する。
気候訴訟における被害・加害の立証
訴訟においては、一般的に、被害・加害関係を具体的に被害者側が立証する義務がある。これは気候変動問題のような排出源が多岐に渡り、かつ将来にもわたる因果関係の決定が容易ではない問題に対しては高いハードルであった。これに関して、ICJ勧告的意見は、気候変動被害と温室効果ガス排出の因果関係や帰属性を「科学的」に明らかにするのは可能とした。
しかし、ここは少し弱いと言うか、少し曖昧な書き方をしているように筆者には思える。そうは言っても、ICJ勧告的意見は、前述のように「化石燃料の生産、化石燃料の消費、化石燃料炭素許可の付与、または化石燃料の補助金供与」を国際法上の不法行為として明記しているので、そのような事実と現在および歴史的排出量の大きさなどで、「科学的」に因果関係などを立証できる可能性がある。
また、ICJ勧告的意見は、自国企業の排出を制限するのに十分に必要な規制措置をとっていない場合も国の不法行為と見做し、予防原則の重要性とともに未来世代への責任も明示的に示した。すなわち、さまざまなかたちで国の責任を問う道筋(ロードマップ)をICJ勧告的意見は提供している。
その他の重要論点
1.5℃目標
パリ協定とグラスゴー協定で、2℃目標および1.5℃目標が言及されているが、その関係は曖昧だった(2℃と1.5℃ではかなりカーボンバジェットの大きさが異なり、必要とされるNDCの野心度も大きく異なる)。
しかし、ICJは1.5℃を各国がめざすべき唯一の温度目標であることを明確にした。このことは、各国のNDCの妥当性を議論する際に非常に重要な意味を持つ。実際には、ICJ勧告的意見は、すでに多くの国に被害が出ているので、「1.5℃でも不十分」とまで書いている。
島嶼国の主権および難民保護
ICJ勧告的意見では、国家が成立した後、その構成要素のひとつが(水没などで)消失しても、必ずしもその国家の主権が失われるわけではないとした。これは海面上昇により領土の完全性が脅かされている小島嶼国にとってすごく重要な点であった。日本にとっても領土問題という意味で重要となる可能性がある。
また、ICJ勧告的意見は、「ノン・ルフールマン(不送還)」の義務、すなわち、気候の脆弱性によって避難してきた難民は保護されなければならず、生命の危険があるような状況下で彼らを母国に送り返すことは許されない、という義務の存在について言及した。
昨年、ニュージーランドにいて環境難民申請をしている人に対してニュージーランドの人権委員会は難民認定とは関係なく、国外退去(送還)するべきでないという判断をしている。今後は、このようなケースがより増大すると思われる。
共通だが差異のある責任と能力の原則
ICJ勧告的意見は、Justice(公正)やEquity(公平・衡平)を多くの文脈で取り上げていて、通奏低音としている。基本的に島嶼国や途上国が主張してきたCBDRあるいはCBDR-RCを重視していて、かつ世代間の公平性についても多くの箇所で言及している。
COPの歴史は、先進国と途上国の間のCBDRの位置付けに関する戦いの歴史と言っても過言でなく、最近では途上国が先進国に押され気味だった。しかし、ICJ勧告的意見がCBDRをかなり持ち上げているので、COPでもCBDRが息を吹き返す可能性が高い。

最後に
ICJ勧告的意見に対しては多くの市民団体がきわめて好意的に受け止めている。その理由としては、内容においてバヌアツなどの島嶼国の要求がほぼすべて通っただけでなく、今回の勧告的意見が、勧告的意見の本文は、裁判所判事全員が合意した、国連総会が要求した質問に対して明確かつ具体的に答えていて曖昧さが少ない、気候訴訟に勝利するための具体的なロードマップになりうる、などがある。
通常、ICJの15人の裁判官の中には他と異なる意見を持つ裁判官が存在し、そのような裁判官は、個別に付加的な意見あるいは声明を文末に載せる。また、往々にして国連文書には「創造的な曖昧さ(creative ambiguity)」がある。今回の文書は、本文は全員一致であり、内容がかなりクリアなものであった。さらに、すべての付加的な意見あるいは声明は、より途上国や脆弱な国の意見を尊重し、大量排出国および先進国の責任を明確に問う内容であった。
このようなICJ勧告的意見に対して日本政府や日本の裁判官がどのように反応するだろうか? 日本の裁判官がしばしば却下理由とする「社会的通念として温暖化問題はまだ深刻な問題にはなっていない」という認識は変わるのか?
予断は許さないものの、温暖化対策という意味では好ましくないシナリオとして「ICJ勧告的意見は単なる意見であり、法的拘束力はない」と日本政府や日本の裁判所が開き直って、ICJ勧告的意見を無視する可能性はある。そうなれば、日本のエネルギー・温暖化政策や裁判所の判断が変わることはない。
しかし、世界では気候訴訟が増大し、国連の主要な司法機関であるICJの勧告的意見にそった政策や判決が増えることは十分に予想される。そうなった場合、日本の政策や「社会的通念」のガラパゴス化はますます加速することになるだろう。それは、ICJの所長が日本人の岩澤雄司氏である事が皮肉としか言いようがないことを意味する。今、歴史のどちら側にいるかが問われている。
@energydemocracy.jp⚖️🌍ICJが宣言:「気候変動は国際法の義務」 — NDCの裁量は✖ — 化石燃料補助金は不法行為になり得る🛢️ — 人権〇/因果関係は科学で証明🔬 — 目標は1.5℃🔥 日本のエネルギー政策&裁判、いよいよ大転換。 #ICJ #気候危機 #1_5℃ #エネルギー政策 #気候訴訟 #気候正義 #サステナブル
- 1ICJ(2025)Obligations of States in respect of Climate Change – The Court gives its Advisory Opinion and responds to the questions posed by the General Assembly, July 23, 2025.
- 2Optimism and outrageous (2025) Planetary News: The ICJ Climate Opinion Explained, July 25, 2025.
- 3久保田泉(2025)法の支配に基づく新たな気候変動対策時代の幕開け—国際司法裁判所の勧告的意見を読み解く, 研究コラム, 国立環境研究所, 2025年8月8日.
- 4外務省(2003)国際法あれこれ, 外務省HP.
- 5地球規模課題審議官組織 国際法局(2024)気候変動に係る諸国の義務に関するICJ勧告的意見手続:口頭陳述, 2024年12月.
- 6Government of Japan(2024)Obligations of States in Respect of Climate Change (Request for Advisory Opinion), Written Statement of the Government of Japan, 22 March 2024.
- 7工藤美香(2025)長期脱炭素電源オークションの有効性を問う, シリーズ「長期脱炭素電源オークションの課題」第1回総論, 連載コラム, 自然エネルギー財団, 2025年7月16日.
- 8気候ネットワーク(2024)世界に広がる気候訴訟 気候変動問題を解決する:司法を通じた道筋, 2024年8月.