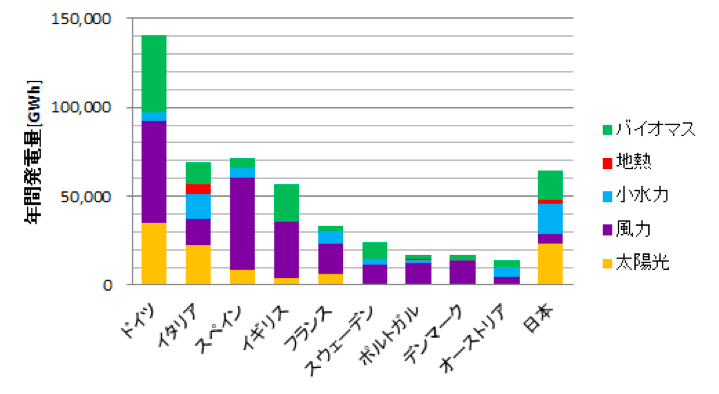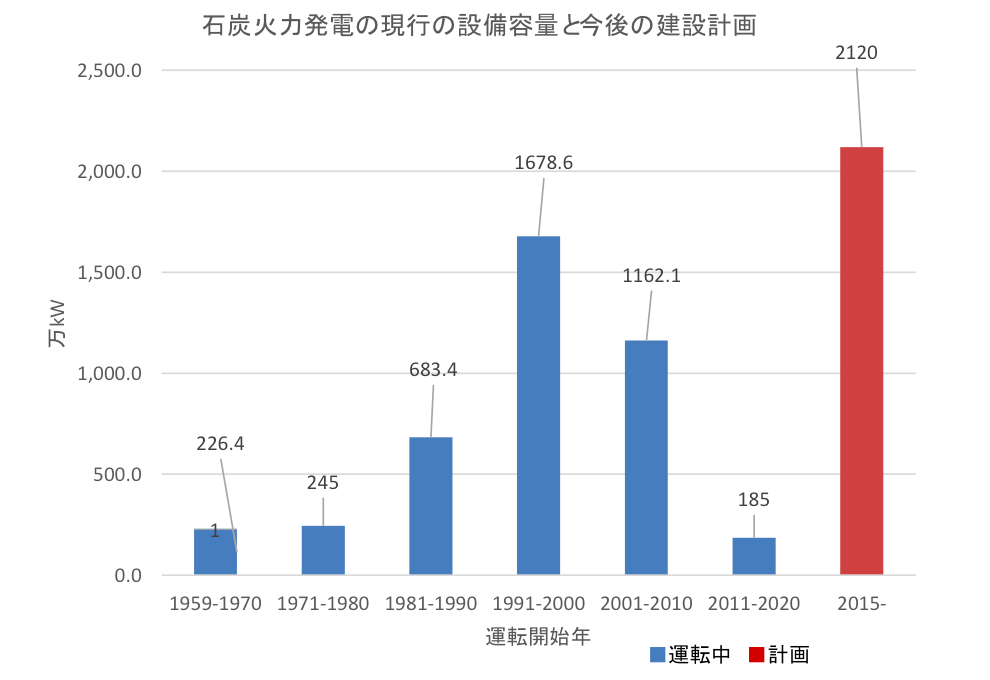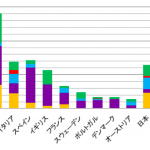昨年12月、スペイン・マドリードで国連の気候変動枠組み条約締約国会議(COP25)が開かれた。最大のテーマは、現在提出されている国別温室効果ガス削減目標を、次COP26(2020年)で引き上げることに各国が合意できるか、決定文書にどれだけ強い表現を盛り込めるかだった。たとえ、いまの国別目標が達成されても、産業革命前からの世界の気温上昇は、今世紀末にはパリ協定の1.5℃はおろか、2℃未満を超えて、3℃以上になる可能性が高いからだ。
結果的に、決定文書に盛り込まれた内容は弱いものになった。米国、オーストラリア、日本などの先進国や、中国、インドなどの新興国が強く反対したためとされる。また、小島嶼国や最貧国などが強く求めていた「損失と被害(Loss and Damage)」についても、目立った進展はなかった。温暖化による被害に対する新規および追加的な資金供与などを含むスキームの見直しについて、拡充する方向で議論していくことになったが、具体的な内容はこれからだ。米国をはじめ先進国は、賠償的な意味合いを持つ資金供与には強く反対している。
中・長期的資金については、主に資金を提供する先進国と主に支援を受ける途上国との対立は激しく、結論はないまま交渉は次回に持ち越された。
パリ協定の実施に暗雲?

2020年から本格的に動きだすパリ協定の実施ルールに関しては、ポーランドでのCOP24から持ち越しになっていたパリ協定6条の行方が注目された。自国で減らせない温室効果ガスを他国に肩代わりしてもらい、その対価を支払う方法で、「市場メカニズム」とも呼ばれる。
その際、削減分を両国で計上すれば二重勘定になってしまうので、どう回避するか。京都議定書期間(2008~2020年)に減らした分(京都クレジット)をパリ協定に流用できるか、が焦点になった。
オーストラリア、ブラジル、インド、中国は、自国が持つ京都クレジットの2020年以降での利用を認めるように要求し、ブラジルは二重勘定も認めるよう要求した。だが、「温室効果ガス排出削減に逆行する」という反対意見が強く、議論は次回に持ち越された。これをもって、パリ協定実施への影響を危惧す声もあるが、6条がまとまらなくても、実施に支障はない。
6条に固執する日本
日本はCOP25で、6条がまとまることにこだわった。なぜなら、日本政府は2国間クレジット(JCM)という独自のカーボン・トレードの制度を実施しており、政治的にも経済的にもすでに大きな投資をしているからである。
このJCMは、京都議定書で決まったプロジェクト・ベースでのカーボン・トレードの制度であるクリーン開発メカニズム(CDM)と似ており、共に、先進国から途上国に資金と技術を提供して、途上国で実施される温室効果ガス排出削減プロジェクトによって削減された分を、クレジットとして先進国が自国の削減分としてカウントできる仕組みである。
ただし、JCMはプロジェクト実施による削減量計算や検証に日本が作った独自のシステムを採用しており、基本的に日本と特定の相手国との2国間のみでの取引である。実質的には日本企業の製品や技術の輸出補助金にもなっており、税金の使い方として適切かどうかの議論は、もう少し必要だと筆者は思う。
いずれにしろ、6条がまとまらないと、JCMの正統性がいつまでも確立されないことになるため、6条にけりをつけることは、日本政府にとって至上命題であった。
「本末転倒」との批判
しかし、温室効果ガス排出削減を進めるという意味では、日本の交渉ポジションは本末転倒という批判も可能である。なぜなら、日本は最終的な局面で、ブラジルが主張した京都クレジットを一部認めるような妥協案を支持したとされるからである。
過剰なクレジットを認めることは、温室効果ガス排出を増加させ、カーボン・クレジットの供給過剰をもたらし、カーボン・トレードの制度自体を崩壊させる可能性がある(実際にCDMがそうだった)。
すなわち、カーボン・トレード制度で最も重要なのは、カーボン・クレジットの需給バランスであり、制度を維持するために不可欠なのが、目標引き上げによる需要の創出である。しかし、日本は削減目標の引き上げの議論には消極的であり、JCMのクレジットが国連の下で正統性を持つことにこだわった。
カーボン・トレードの制度自体は、2℃目標を達成するという大きな目的においては、たくさんある手段の一つに過ぎない。日本政府のCOP25における6条に固執したポジションは「目先の国益しか考えていないものであり、パリ協定の全体目標の達成やカーボン・トレードの制度全体の環境十全性を考えていない」「木を見て森を見ず」と、批判されても仕方ないと思われる。
COP26に向けたEUの戦略
2020年11月にイギリスのグラスゴーで開催されるCOP26は、5年毎に目標の見直しを決めたパリ協定の採択から5年後にあたる。最大の焦点は、各国が目標を引き上げるかどうかである。しかし、現在、主要国で目標引き上げの意思を明らかにしているのはEUのみである。
米国がパリ協定からの離脱手続きに入る中、EUはしきりに中国に対してプレッシャーをかけている。2020年9月、ドイツのライプチヒでEU・中国サミットが開催される。EUはそこで中国とともに何らかのメッセージを出したいと考えている。
そのため、EUはCOP25の期間中、2030年の温暖化ガスの排出削減目標を引き上げる方針を示した。従来の1990年比40%減から50%減に引き上げ、さらに55%をめざす。また、50年に域内の排出を実質ゼロにする法案を、20年3月までにまとめるという。
温暖化対策に消極的な国に対しては、関税をかけるような措置(国境税調整)を、EUグリーン・ディールの一要素として提案した。念頭にあるのは米国などだろうが、日本もこのままでは温暖化対策後進国として国境税調整への対応を迫られる可能性がある。
全会一致というくびき
そうは言っても、グラスゴーで交渉がまとまるかどうかは全く楽観できない。COP交渉では、全会一致主義がとられている。一国でも反対する国がいると、交渉は前に進めない。前に進めるためには、合意内容を最も消極的な国に合わせなければならない。それは必然的にバッド・ディール(悪い合意)になり、多くの国がノー・ディールを選ぶ、すなわち決裂する可能性は小さくない。国連の下での交渉の限界を示している。
しかし、他に良い代替案がないのも事実だ。多数決にも問題がある。「民主主義は極めて多くの問題を持つ制度であるものの、他のどの制度よりもましである」と似た状況で、しばらくはこのシステムでやっていくしかない。企業や自治体などの非国家アクターの役割は重要だが、あくまでも必要条件であり、十分条件ではない。
怒りの昇華
このような「どん詰まり」の状況を、どう変えるか。一つのレスポンスが、若者たちによる怒りの行動なのだろう。2020年は、世界中で若者によるアクションがより一層盛んになるだろう。2020年4月22日のアース・デーの前後には、昨年9月のように何百万人が街に出て、大きな声をあげると予想される。
もちろん、それも十分条件ではない。怒りを政治的モーメンタムに変えて、政治や政策のレベルまで持っていく必要がある。怒りの昇華であり、それには、大人が頑張るしかない。
WEBRONZA「やばすぎて目が離せない COP25から26へ(2020年1月21日)」より改稿